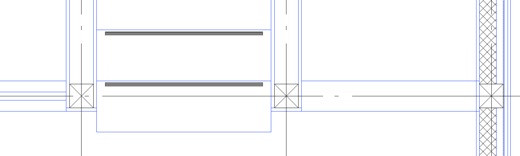
▼ -3.会報誌(風に吹かれて) の記事一覧
1993年、秋。バブルがはじけた後の不況のまっただ中だった。
私の勤めていた企業でリストラがあった。
1157人の社員に対し、250名希望退職者を募った。
1/4弱の社員を整理したいとのことだった。条件が提示された。
いくつかの条件の中で、ある条件がひときわ輝いて見えた。
当時私は、その会社に借金をしていた。
退職金を全てつぎ込まないとその会社から逃れることが出来なかったのである。
別にその会社から逃れる必要はなかったのだけど、そういう意味で自由がきかないことに不満を感じていた。
「希望退職者には、退職金を2倍支給」
とっても輝いて見えた。
それまでの不自由が一気に消えて行くかのようだった。
すぐに手を挙げた。
かといって、それから先の保証は何もなかった。
しかし、保証の代わりに自由を手に入れることを選んだ。
30歳をめどに仕事のスタンスを自分なりにシフトしていこうと決めていた。
何度もこのエッセイに書いてきたことだが、30歳までは、吸収。
30歳を過ぎたら、吸収と吐き出し。
この吐き出しが、自分自身の存在証明だった。
その当時、私は32歳。
その吐き出しの反応に少し不満を感じていた。
ある長期プロジェクトだった。
クライアントの担当者とは、もうかれこれ4年ぐらいのつき合いになっていた。
ある程度気心も知れ、こちらの熱意や力量も充分知っていた。
企業と企業のビジネスとはいえ、やはり担当者レベルで歩調が合わないとプロジェクトは成功はしない。
歩調は充分あっていた。
それまでは「佐山さん、佐山さん」と私のことを名前で呼んでいた。
しかし、ある問題を真剣に議論しているときだった。
お互いに一歩も引かずに平行線をたどっていた。
そのプロジェクトにとってよかれと思うことをお互いに議論していた。
突然、「ねえ、T社さん。君の言っていることはわかるけどねえ。」と言われガックリしてしまった。
また、別のプロジェクトでも同じようなことがあった。
こちらのイメージ提案の内容をクライアントに説得するために、自分なりの考え方をかなりの量の企画書にまとめ、理詰めでプレゼンテーションに望んでいった。
ひとしきり説明がすんで、相手の反応を待った。
何か相手の顔色がおかしいのである。
「あなたの言っていることはわかるけど、いつものT社さんのイメージ提案でいいんだよ。」
そんな理論展開をお宅の会社になんか頼んでいるわけではない。
そんなのは10年早いんだ。といいたげな様子だった。
それらの瞬間、企業の一員であることの再認識と企業の一員であることの限界を感じてしまったのである。
結局、自分の存在証明を得るために自分なりのやり方なり考え方で進めていくためには企業にいては限界があるのである。
なぜならば、クライアントは私個人に仕事を依頼しているわけではなく、あくまでもT社という企業に仕事を依頼しているからなのである。
時と場合で、個人の顔は邪魔な場合がでてくるのだ。
こちらは、T社に所属しながら、一人の人間「佐山」として、そのプロジェクトにとって一番よかれと思っている内容を提案する。
しかし、時と場合によって、佐山個人の顔が邪魔になってくる場合もあるということらしい。
また、こんな経験も積んだ。
別のビック・プロジェクトでの話である。
ある日本の商業施設の建築設計者として世界でも有名なアメリカの建築家が参加するというプロジェクトだった。
こちらは、日本の商業施設設計のプロとしてプロジェクトに参加していた。
そのアメリカの建築家は、そのプロジェクトの事業主であるN社の社長が気に入って、そのプロジェクトに参加させたという前ふりだった。
プロジェクトが進むにつれて、やはり斬新なデザインの建築全体像が現れてきた。
N社の社長もそのデザインが気に入ってご満悦な様子だった。
そのプロジェクトでは、その建築家が基本設計までを担当し、それから先の業務は施工を担当する日本のゼネコンと私の所属するT社で受け持つことになっていた。
進行するにつれて、斬新なデザインのために事業費がかなり膨らんでいった。
実施設計以降を担当するゼネコンとT社で再三に渡り、コストコントロールを重ねていったが、はるかに予算をオーバーするものとなってしまった。
もうコスト的に調整がきかない段階まで行き着いた時点の全体会議の席上で、実行部隊側は、そのアメリカの建築家にデザイン変更を求めた。
帰ってきた言葉を聞いて、愕然とした。
「それなら、なぜ私を建築家として選んだのだね。」
「私のデザインがほしくて、私を指名したのではないのか。」
つまり、彼のデザインでやる以上は、もっと予算を計上しろ、それができないのであれば、私は降りると言いたかったらしい。
N社の社長は、腕組みをして黙っていた。
その建築家の個性、つまりその建築家の顔で仕事をしている以上、そのキャラクターを大切にしてくれと言うことなのだ。
そこのところを理解しないで仕事を依頼するな。ということらしい。
いろいろと経験を積むうちに、クライアントのために全力投球しそれに応えるためには、やはり自分自身で仕事を請け負うしかないのかと思うようになっていった。
まだまだ、未熟者ではあるけども、佐山個人のキャラクターを理解し、佐山個人に期待してくれるクライアントに対して全力投球していくことで自身の存在証明を得ていこうと考える様になっていった。
そこで、退職金倍支給のリストラがあったのである。
私には、「渡りに船」と感じた。
すぐに手を挙げ、何の保証もない力の世界に飛び出していったのである。
自分で引いた、生きていくためのレールに沿って、より充実した「吸収と吐き出し」の日々を重ねるために、いよいよ自ら喜んで飛び出していったのである。
つづく。
平成9年8月 小潮
あとがき
一回こっきりの人生なのだ。
自分に対して、「正直に」生きていこうと思った。
楽な道ではないけれど、直球勝負でいきたかった。
やはり、建築設計をするものは、「生きる」ことを真剣に楽しまなければ、つとまらないと考えていた。
建築って、すまいも、オフィスも学校もお店もすべてみんな「人間の第3の皮膚」なのだ。
そこで、どういう営みがおこなわれて、なにが不足で何が無駄なのかを理解体験するには、その空間を楽しまなければならないのだと思っている。
よく写真とかですごくカッコ良く写っている空間を見に行くと、がっかりすることがしょっちゅうある。
いい意味での生活感がなかったり、いとなみの姿が見えなかったり、空間が美しく歳を取っていなかったり。
やはり、日々の生活をサポートするのが、建築のあるべき姿だと考える。
そうすると、朝から晩まで会社にいて、家には帰って寝るだけではイカン!と単純に思ってしまって、会社を辞めてしまった。
日々の生活をしっかりと楽しむことが、自分の建築キャラクターを成長させる回り道と勝手に決め込み、今に至っているのだ。
その「思いこみ」は、いまのところ大きく間違ってはいないようだ。
2000.09.25
1989年、3つのデザイン賞をいただいた。
前号で紹介した、Tドームの「新業態店舗」、M社の「新規事業開発店舗」、D社の「アンテナショップ開発計画」が受賞した。
「売れる店」「新規事業の柱となる店」を創れというオーダーのため、どの計画も店舗設計というよりは、商品、サービスの新規展開に重点を置いた店舗開発だった。
店舗デザインは、売れる店をつくるための手段でしかなかった。
しかし、それらのどれもがデザイン賞をいただいたのである。どの物件も苦労した2年越しの長期物件だったので喜びもひとしおだった。
第2の修業の場として転職して3年目で手にした社会的評価だった。
今にして考えると少し早かったかもしれない。
何故ならば、賞なんて簡単に取れるとタカをくくってしまい、変な自信がついてしまったのである。
それからは、なかなか社会的に認めてもらえる結果を出すことが出来なかった。
毎年「今年も賞を」と思いつつ、いくつか新作をリリースするのだけど全く認めてもらえなくなっていった。
確実に巧くなっているはずなのに認めてもらえないので不思議だった。
しばらくして気がついた。
大きな落とし穴にはまっていたのである。
転職して右も左もわからず、がむしゃらに進んでいたときと仕事への姿勢が違っていたのである。
どうやら小手先で仕事を進めていくようになっていたようなのである。
このことに気がついたのは、転職して5年目あたりだった。デザイン賞をいただいてから3年ぐらい経った頃だ。
やはり、どんな世界にもジンクスがある。
新人賞を取った次の年は活躍できないとやらである。
心のどこかに「そんなものか」といううぬぼれや変な自信が出て来るのだろう。
そして、それまであった、がむしゃらに前に進もうとするハングリー精神や探求心が一時的に無くなってしまうのだろう。
私の場合もそうだった。
気がつくとうぬぼれと変な自信が心を支配しており、前向きな姿勢が失せていた。
まだまだヒヨッコの私が、俗に言う天狗になっていたのである。足もとを完全にすくわれていた。
そのことに気がついてからは、また足もとを見つめながら着実に吸収の日々を送ろうと決心した。
1991年、春。
気の合う仲間同士で八丈島に行った。
北海道の山の中で育った私は、自然の中で遊ぶのがとても心地よかった。
その時は、2泊3日のキャンプ生活だった。
もう2度と帰りたくない、またいつもの仕事生活に戻りたくないと思ってしまった。
6人で行ったのだが、全員で「帰りたくない」「帰りたくない」と大人げなく言い散らしていた。
南の島特有のハイビスカスの赤い花、夕刻にたたきつける激しい雨、一定に吹き続ける心地よい風。
そんな中で、ほんとうに帰りたくなくなってしまっていた。
海を見つめ、風に吹かれながら、自分はいったい日々何をしているんだろうとぼんやり考えていた。
都会の中で、毎日毎日通勤地獄に身を任せ、山積みになった仕事へと挑んでいく。
その一日が終わる頃には、ヘトヘトになり山積みの仕事を横目にしながら飲み屋へと消えていく。
会社員なので気を抜いても多少さぼっていても給料はもらえる。
自分の興味のあることではなくて与えられた仕事をこなしていく。
このままでいいのだろうか。
自然の中に身を任せていると自分自身も生物の一員なのだとあらためて思うことがある。
容赦なく降り続ける雨、丸い地平線、今にも落ちてきそうな夜空の星。
どれもが、人間のスケールを超えた大きなものに見えてくる。
日々、会社の中で思い悩んでいることがとてもちっぽけなことに思えてくる。
目先のことだけではなく、自分自身を見つめ遠くを見ようじゃないかと自分を叱咤したくなってくる。
自然の力は大きいのである。
足もとを見つめながら着実にやろう!という気持ちと、遠くをしっかり見定めよう!という気持ちがたまたま一緒になってしまった。
30歳までは吸収の日々、30歳から40歳までは吸収と吐き出しの日々、40歳から50歳までは吐き出しの日々、そして50歳からは山にこもって仙人的建築家生活。
と社会人1年生の時に決めた人生の白図があった。
八丈島で自分が生物に戻ってしまったそのころ、ちょうど30歳を迎えていた。
そろそろ自分で決めた転機である。仕切なおして出直そうと思った。
吸収することだけでは飽きたらなくなってきていたところだった。
吸収することはまだまだ続けるけれど、吐き出すこととはなんなのか考えるようになった。
基本的には、社会貢献できることであることの様な気がした。
自分の少ない経験で社会貢献できることといったら何があるだろう。
男30歳といってもまだまだヒヨッコである。
少なくとも建築の世界では、50歳までは、見習いである。
50歳を過ぎた頃から経験と判断力が熟しはじめて、肩の力が抜けた良いものが出来るようになるといわれる。
建築を武器に社会貢献とは、まだまだおこがましい様である。
いろいろ考えた。いっそ今まで建築的なことや商業施設の開発的なことを吸収してきたけれど、自然に抱かれて生計を立ててみたいので第一次産業の道に進もうかとも考えた。
農業、漁業、林業。体力勝負の男らしい職業に見えた。
中でもイート・フィッシャーでもある私としては、漁師の道を真剣に考えた。
一方、せっかく10年以上建築的なことに携わってきたのだから、その道を全うしないのはもったいないという思いもあった。
10年続けているとひとつのスタイルができあがるといわれている。
もうそろそろ自分なりのスタイルが見えてくる頃である。やはり、もったいないような気がした。
自然と共存の上になり立つ漁師、かたや自然に立ち向かう建築家(いや、自然を壊す建築業)。
相いれない指向性を持った職業に思えてきた。
自然と共に生きていきたい人間が、建築を生業として生きていく。
何となく矛盾している。
こんな人間がすぐに活動できる場は当時まだ少なかった。
今でこそ、環境問題やハウス・シックの解決法が求められるようになったが、自分がT社で担当していた仕事の中でもそのような仕事はなかった。
しかし、少しだけ見えてきた。青い海を見ながら、心地よい風に吹かれて、人間が生物に戻れる瞬間がいかに素晴らしいことであるか。
自然の中で、人間らしさを取り戻すことが、いかに前向きに生きていくことに必要なことか。
そんなことを自分なりに解釈して日々の設計活動に生かしていこうと考えたのである。
やることは、たくさんあった。
環境保護活動、自然と建築の接点探し。
吸収は、建築。
吐き出しは、自分の持っている自然感。
自然の持っている素晴らしさを伝えることは、30歳の私にも出来る。そう決めた。
そう決めると、以外と見えてきた。T社の業務の中にも自分を行かせる仕事が時たま出てきた。
1992年、夏だった。
幕張の新興オフィスビル街の一角に巨大なオフィスビルの計画があった。
私の担当は、そのビル自体の全体環境の方向性を提案し、ビルのデザイン的性格を決定していくという仕事だった。
今でも覚えている。
たまたまニュースで幕張の埋立地が整備されていき、南方からやってくる「コアジサシ」という渡り鳥の繁殖地が激減していると報道された。
私が担当していた幕張のオフィス・ビルのあたりらしかった。
すぐに次の日、TBSのそのニュースの担当者を訪ねた。
「昨日のコアジサシ・ビデオ・テープを貸してください。」理由を話すと担当者は快く貸してくれた。
その足で、環境庁を訪ねた。
昨日報道された「コアジサシ」の件を話し、内容の裏付けを取った。
確かにほんとうらしい。
その日、会社に戻り「日本野鳥の会」に問い合わせ、人工的に「コアジサシ」を繁殖させることは出来ないかを訪ねた。
できるらしい。
取り急ぎ資料をまとめた。
翌週、そのオフィスビルのデザイン会議の時に、収集したビデオなどの情報や具体的にデザインに取り入れる方法論をプレゼンテーションした。
会議の席上、列席者の中で反対する人はいなかった。
人間のために水辺をビル環境の中に取り入れることはあっても「渡り鳥」のために水辺を取り入れることはなかったはずである。
それも人間と水辺をある程度隔離し、人間の気配を取りたちに感じさせないようにするのが肝心らしかった。
そうなると誰のための水辺なのかということになってくる。
勿論それは、「コアジサシ」のためだった。
反対者はいなかったものの我々の提案は、やがて人間のための水辺に少しずつ姿を変えていったようだった。
我々は、提案レベルでそのプロジェクトの役割は終了したので結末は見ていない。
しかし、そのプレゼンテーションの時に列席した人たちに何らか時流のパラダイムシフトを感じていただけたに違いないと信じている。
また、ちょうどそのころ、某旧国鉄の開発担当社へ向けての社員研修の講師の依頼が来た。
私の担当は、環境計画の実戦という講義内容だった。
その時私は、私が得意とする小規模の店舗開発の進め方から大規模なランドスケープの開発の進め方を約2時間程度にわたって講義を行った。
大規模な開発の話では、地球の環境をいかにして改善していくかというような話を先進事例を紹介しながら行った。
地球を守ろうとかいうのは、おこがましい。
地球は自ら自己治癒能力を備えているので、人間は今以上に環境が悪化しないような努力をしなければならない。
また、都市部では、森林や雑木林が減り、ヒートアイランド現象がおこっている。
そのことによる弊害が、人間の体までをむしばんでいる。
だから、都市部にこそ緑を増やさなければいけない。ビルの屋根には、緑を。
大きな通りには、並木を。
都市全体に緑を増やすことが、地球と人間を共存させるひとつの方法だ。
と力説した。
私の講義が終わり、その他の講義もいくつか行われたあとで開発計画の課題が与えられた。
私は、講義を行っただけでその場をあとにしたが、課題の結果は、30人ぐらい研修者がいたが、ほとんど全員、敷地いっぱいに緑を埋めこんだらしい。
中には、課題の敷地が大阪駅の裏という設定にもかかわらず、動物園を計画した方もいたらしい。
その話をあとから聞いて、私はうれしかった。
一度は、デザイン賞をいただき天狗になって足もとをすくわれた。
しかし、自分の役割に気付き、一歩一歩自分らしさを吐き出し始めた。
吸収することに専念していたときとは違い、手応えを感じた。
「コアジサシ」、「都市に緑を」どれも敏感に反応してきた。
自分の考え方に賛同してくれたのである。
このころ天狗になっていた頃とは違う自信がすこしずつ沸いてきた。
また、心地よい自然の中で遊び続けたい私自身の建築を通じてのメッセージが少しずつ周りに伝わり始めてきた。
自分自身の道を『自信』と『自身』で切り開いていくことが、愉しくなり始めていった。
つづく。
平成9年7月 大潮
あとがき
ああ、なつかしくも、つらく、楽しい日々。
今となっては、懐かしく感じられるが、当時は真剣にもがいていた。
今の私を形づける基礎となった話なのである。
今も、かわらず、おなじ基盤の上で、もがき苦しんでいる。
2000.07.10
1986年5月、住宅メーカーから内装・ディスプレイ業界最大手のT社に転職した。
手の内の駒を増やすことを考えての転職だったので業務の全てが初めてづくしだった。
望んでいたこととはいえ社会人4年生でもあったので「わかりません」では済まされず、自らどんどん吸収・消化していかなければならなかった。
それはそれは、苦しくても愉しい修業の日々だった。
私が、第2の修業先で所属したのは商業施設の企画開発部門だった。
当時、バブル経済のはしりの時期だったこともあっていろいろな仕事が次々と舞い込んできていた。
右肩上がりの経済事情でもあり、大手企業の新規事業開発の仕事が多かった。
その中でも強烈に印象が残っている仕事があった。
本誌を読んでいる起業家や予備群の方々にもとても有益な話であろうと思うので惜しげもなく披露したいと思う。
それは、都内某所のKスタヂアムからTドームへと変貌する際の商業施設計画だった。
それまでのKスタヂアム時代は、売店と呼ばれていたキオスクスタイルの小さな個店が要所要所に散らばっているだけの商売のやり方だった。
しかし、場所が場所なので瞬時には数万人というお客が集結し、お祭り気分に浸って衝動買いをするという異常な盛り上がりを見せることもあってその商売のやり方でも売上は相当のものがあった。
そういう商売的にはいい状況の中であえて、Tドームという日本でも初めての全天候型一大イベントスペースに生まれ変わるにあたり、商売のやり方を見直すことになったのだ。
それも『売上倍増以上指令』が、出されたのだ。数字的には、当時年間4(よん)の売上を10(じゅう)にしろという厳しい指令が出されたのである。
予測される観客動員数は、プラス25パーセント強。
即ち訪れるお客様の数は、4が5に増えるだけである。
そのような状況で売上だけは、『4を10に』という厳しい条件だった。
その第2の修業先に転職するまでは、住宅を建てるお客様の「夢の道先案内人」としての修業しかしていなかったので、お店の売上を上げるなんてことは皆目わからないことだらけであった。
必死に勉強、吸収した。
その仕組みや仕掛けが次第にわかってくるにつれて、ひとつひとつ手の内の駒が増えていく実感があり、苦しくも愉しかったのを覚えている。
当時、東京ディズニーランド(以下、TDL)の物販店が大盛況を納めていた。
TDLが、出現するまでの遊園地での物販店の形態は、やはりTスタヂアムのようなキオスクスタイルの売店程度のものだった。
しかし、TDLの物販店は違っていた。
何が違うのか。
良く観察することから始まった。
まず、商品が違っていた。
TDLで展開されている様々なアトラクションのキャラクターが勢揃いし、小さなキーホルダーから等身大のぬいぐるみまで様々な商品に反映されていた。
一日遊んでその思い出をそれぞれの嗜好に合わせてお持ち帰りいただけるようにあらゆる商品に展開されていた。
小さな子供からお年寄りまで徹底的にお持ち帰りできるようになっていた。
それらの商品を持ち帰ることによってTDLの余韻を家でも楽しめるようになっていた。
単なるおみやげ店の売上が上がるだけではなく、TDLの年間入場パスポートが売れている背景にこれらのおみやげ品も一役買っているのであろうと思われる。
次に、売り方も徹底していた。
何が徹底していたのかというと演出的なのである。
あたかもアトラクションの一員が売場に出てきて売っているような感じなのである。
非現実感を演出することで気分を現実に戻すことなく、錯覚の中で財布の紐をゆるめさせるテクニックがそこには存在していた。
基本的には、おみやげ品である。
実生活上で必要な商品ではないのである。
ハッと我に返る瞬間があれば、「やめとこ」となってしまう商品群なのである。
話はそれるが、宝石店などもその典型である。
生鮮食料品とは違って生活する上で必ず必要なものではないのである。
宝石店の場合のテクニックは陳列什器が途切れないようにすることである。
一番望ましいのは、ガラスケースをドーナツ状にしてガラス面から顔を上げる瞬間をなるべく少なくすること。
顔を上げて深呼吸する瞬間をつくってしまうと「やめとこ」になってしまうケースが多い。だから途切れないようにするのである。
話を戻すが、売り方の次にTDLは、売場その物の空間も徹底的に演出していた。
売り方同様、アトラクションの一部が売場になっているのである。
そこは、ワールドバザールと呼ばれ、TDLのなかでもおみやげやが集中しており、仮想物語上のマーケットになっていた。
それも入口近く、逆を返せば出口付近に繰り広げられていた。
一日遊んでまだ遊び足りなくて後ろ髪を引かれる思いで帰らなければならない人たちを待ち受け、送り出すにはふさわしい場所に形成されていた。
商品、売り方、空間構成、理にかなっており、TDLのおみやげ品は売れないわけはないのである。
お客様の望むものを気分を盛り上げたまま最高の立地で買っていただくのである。
売る方も買う方も大満足である。
喜んで買っていただくことが先である。
売上を伸ばすことが先ではないのである。それは商売の原点であるとみた。
TDLの物販店を調査分析して何となく商売の原点を見たような感じがした。
そのTDLの調査などは、業界用語では、マーケティング・リサーチ(市場調査)といわれる。
類似例を調査して方向性を導き出すのだ。類似例を知り、その長所、短所を分析して新規事業の手本とする。
これから起業しようとしている人、すでに起業しているが、いまいち伸び悩んでいる人などは、類似業種を良く観察して長所短所を整理してみると良い。
なぜ、業績が上がっているのか、なぜ業績が落ち込んでいるのか、観察してみると良い。
現在でも私のところに依頼されてくる「売上を上げたいのだが、どうしたらよいか」などという物件は、類似例の調査から始めることにしている。
そうして分析を重ね、大きく常にシフトしている世の中の流れを見つけだすのである。
ただし、同じことをやっても効果的ではない。その時々で、よりベターな味付けをしていくことが大切なのである。
Tドームの場合もTドームに一番あった味付けを試みた。
それも視点はズバリ3点に絞られた。
商品(品態)、サービスの仕方(業態)、そして店舗形態(店態)の3点である。
今現在の私の商業施設の取り組み方もこのときに学んだやり方を踏襲しており、しっかりと手の内の駒になっている。
商品構成は、それまでの野球応援グッズだけだったものからTDLの事例や世の中の流れを見て大きく変えた。
Tドームになると周辺一体がシティリゾートとして機能し始めることが予測できた。
野球観戦の人や場外馬券を買いに来る人だけではなく、シティリゾートを楽しむためにやってくる人の動員数もバカに出来ないと踏んだのである。
約1年半の検討の末、従来の野球応援グッズの他に、感性を大切にした商品群、遊び心を大切にした商品群、まんじゅうに代表される手軽なみやげの食品群の新しい3つの商品群を導入することになった。
サービス形態は、キオスクスタンドのため銭スタイルから専門店方式のレジカウンタースタイルに変えた。
このお金のやりとりの方法ひとつでそのお店の店格ががらりと変わるのだ。
店格というと馴染みがないかもしれないが、お店にも格があるのだ。私もその時初めてそのことを知った。
言葉にすると馴染みはないが、確かにそれぞれ個人個人でこんな場合はあのお店、あんな場合はこのお店と使い分けていると思う。
『TPOに応じて使い分ける』それは、店格があるから使い分けることが出来るのだ。
飲み屋を決める場合も『居酒屋』にするか『カラオケ・パブ』にするか、はたまた『ホテルのバーラウンジ』にするかケースバイケースで使い分けている。
話はそれるが、起業している方々も実は、格付けされているという事実に気付いているだろうか?自分の企業が世の中でどう位置づけされているか客観的に見てみることは必要であろう。
得てして自分のことは見えないものである。
自分の望んでいるまたは目指している企業像と世間が評価し格付けしている企業像と合っていることが望ましいが、ずれていると判断したら軌道修正が必要だ。
自分のところは、『居酒屋』なのか『ホテルのバーラウンジ』なのかは見きわめておくことが肝要である。
そして見きわめられたら徹底してその格の中で勝負することが勝利への道なのだ。
Tドームの場合も基本的にはおみやげ屋だった。
格を少し上げてもおみやげ屋には変わらない。
高級百貨店ではないのである。そこのところは、非常に大切であった。
その点を留意しながら、店員教育も約1年かけて徹底的に行った。
次に点在していた店舗を1ヶ所に集中して運営するということも難題として課せられたテーマだった。
それまでは、人の溜まりそうなところには必ず売店が配置され効率よく商売が成り立っていた。
それが、Tドームが完成する時点では、70坪の1ヶ所のみが売店として設定されているに過ぎなかった。
それもTDLの様に効果的な場所に配置されているわけでもなく苦戦が予想された。
しかし、我々がそのプロジェクトに参加した時点ではどうにもならなかった。
『売上4から10へ』の指令は、日々重くのしかかっていた。
転職早々、馴れない商業施設の売上拡大というテーマに悶々と格闘していた。
それも一級建築士の私が、売上拡大策を日々検討しているのである。
『急がば廻れ』とはこのことかもしれないと思った。
いずれこのことも大きな武器となるのだと言い聞かせ畑違いのことに立ち向かった。
少し客動線からはずれた70坪の店舗だけでは、売上が大きく伸びないと感じていた。
上司と検討に検討を重ねた結果、ゲリラ的に出没する演出された屋台で売上を伸ばそうということになった。
この計画は、その後マスコミに一部取り上げられたこともあるので知っている方もいるかもしれない。
それらは「ワゴンマスターズ計画」、「パンドラボックス計画」、「キオスクス計画」、「オレンジトレイン計画」、「ストリーキングス計画」と名付けられ事業主にプレゼンテーションを行った。
この考え方は、オープン後どう流れるかわからない客動線にたいし、直接店舗をぶつけていこうというものだった。
演出効果も考え、売上にも貢献させようとするのだ。
事業主側も反対する理由はなかった。
5つの計画案の内、「パンドラボックス計画」と名付けられた移動販売車計画が採用された。
普段は、建築やインテリアのデザインを行い、図面化している人間が、車のデザインをするのだ。
これは、外科の医者が、お腹が痛いと言ってやってきた患者を診るようなものだと思って好いだろう。畑違いなのである。
しかし、その時点ではプロジェクト予算が決まっていた。
車輌費が予算計上されていなかった。それで自ら企画書を手に車輌を提供してくれそうな大手自動車メーカーへ何軒も廻った。
この営業的な行動は、第1の修業先である住宅メーカーで学んだものであった。
バブル期とは言え、どの主要自動車メーカーからもいい返事がもらえなかった。
最後に飛び込んでいったM自動車が具体的に検討してもかまわないと言ってきた。
具体的に先が見えたのでデザイン作業にとりかかった。
延々と徹夜が続いたが、とても愉しかった。もしかしたら、これで『売上倍増以上』指令が達成できるかもしれないのである。希望にあふれていた。
あらゆる視点から『売上倍増以上』指令に取り組みTドームがオープンした。
オープン直前、徹夜で商品陳列やディスプレイに取り組んだ。開店秒読みまで最後の調整を行っていた。
オープン後、自分が約2年間試行錯誤を繰り返して取り組んできた店舗に、行列をなしてお客様が吸い込まれていく姿を見て背筋がゾクゾクしてきて止まらなかった。
興奮した。それまでの苦しみは、全て吹き飛んでしまっていた。
自分が初めてデザインした「パンドラボックス」の周りも人だかりで埋まっていた。
うれしかった。
我々で新しく導入したいろいろな商品も飛ぶように売れていく。
『とても良い回り道を経験した』と喜びをかみしめた。
この商業施設計画は、専門業界からも評価され’89ショップ・システムコンペティションに入選するというおまけも付いた。
それより何より、一番うれしかったのは、オープン後1年経過した時点で事業主に呼ばれて、次の話を聞かされたときだった。
担当者は、ニコニコしていた。
『次の店舗開発も君たちに任せたいのだが』
『開店前は、4だった売上が、1年目締めてみたんだが、なんと25まで上がっていたよ!』
予想以上だった。
第2の修業先で一番目に習得したことはお店の設計とは『売上拡大』のためにすると言うこと。
だれも『カッコのいい店』を望んでいるのではなく、『売れる店』を望んでいるということ。
今でもその鉄則は、この生活空間研究所に活きている。
つづく。 平成9年6月中潮
あとがき
もう、14年前の話である。
建築設計者が商売の基本を学ぶ機会はそうそうあるものではない。
「急がば、廻れ」との格言があるが、満を持しての転職は、とても有意義なものとなった。
そして、仕事のおもしろさと厳しさも同時に学んだ。
商業施設は、「売れてナンボ」の戦場設計なのである。
いかに気持ちよく財布の紐をほどかせるか、お金を使って良かったと思ってもらうか、これが肝心である。
かっこいい店は、誰でもつくれるが、売れる店はなかなかつくれない。
空間だけが立派でも繁盛しない。
市場を見極め、商品を厳選し、売り手の姿勢がしっかり伝わって、初めて繁盛するのである。
いまでも、商業施設の設計依頼があると、マーケティング、マーチャンダイジング、サービス形態を討議検討し、方向性が見えてからでないと戦場設計に取りかからない。
廻り道をしたおかげで、とても大きな手のうちの駒が、ひとつ手に入ったのである。
2000.07.07
前回は1986年に決行された第2の修業先への転職物語だった。
今回はその続きではなく、今一番関心のあることについて書くことにする。
というのも、ここんところこの「起業家」は、しばらくリニューアル休暇となっていたので、実はこのエッセイも一年ばかり休暇していたのである。
そんなわけで編集者から「まだ書けないのか!締切はもうとっくに過ぎているぞ」と毎日催促が入っているのだが、前回の続きになかなか入り込めなくて苦しんでいたのである。
私のエッセイの第1回目を読んで頂いた方は、「風に吹かれて」のタイトル主旨を知っていると思う。
このエッセイは私の起業にいたるまでの話をベースに進めるけれど、その時そのときの状況で、風に吹かれるように話の内容があっち行ったりこっち行ったりするが、肩ひじ張らずに興味のあることについて書いていこうと決めたのである。
だから、今回は前回の話に続いていかなくても誰も文句が言えないのである。
このエッセイを書き始めたのは1995年7月だった。
その時点では、創業1年目、社員は社長一人の超零細企業だった。
企業とは名ばかりで、一人親方の気ままなやり方で仕事をしていた。
そうそうスケジュールがびっしりと詰まっているわけでもなかった。
その日やることが済んでしまえば、社員の給料の心配なんかもする必要がないので、いそいそと釣りに出かけてはボ〜っと企業の理想像やら職業哲学なんぞを考えていた。
ところが、今ではおかげさまで私の他に社員4名となり、なんと4月から新卒の新入社員まできていただくコトとなった。
部隊は総勢6名。
総勢1名の時点で、桃太郎のもとに犬君がやってきた時には、鬼退治をするには猿君とキジ君も必要だなと考えていた。
しかし、総勢6名となると「7人の侍」いや「荒野の7人」まであと一人なのである。
トップに立つ者の統率力によって、部隊の生死が決まるのである。
状況判断を誤り、「トツゲキ〜!」とやってしまったら、全員切られるか、撃ち殺されてしまうのである。
それぞれの能力を把握しながら「おまえは、見張り役」「君は、探り役」「あなたは、切り込み役」と長所を生かしつつ、部隊を前進させなければならない。
そこで、隊長にとって一番大事なのは、それぞれの適所に適材を配置することもさることながら、なんのために部隊は戦うのかというコトをしっかりと伝えるコトなのである。
「鬼を退治するために鬼が島へ向かうんだ」とか「村の人たちを盗賊から守るんだ」等をしっかりと伝えることだと思う。
けっして、「鬼が島に行くことが目的ではない」とか、「盗賊を殺すことが目的ではない」ことを全員で確認し、同じ目的のために一丸となって動くんだということを共通認識として浸透させる必要がある。
今、ある企業の博物館の企画、設計の業務を請け負っている。
その企業は、総勢1300名の部隊である。創業者が1代でもって育て上げた立派な複合部隊である。
そんな大所帯を立派に前進させている隊長にも悩みがあった。
約50年前、その隊長は子供の頃から苦労をして、学校教育も満足に受けずに宮大工に弟子入りした。
宮大工の修業時代には、伝統古来の匠の技をしっかりと習得した。
修業の時代が終わったところで田舎町から都会に出て、独立することとなる。
その地方の特徴は、雪が多いせいもあり冬期間、土木・建築の仕事は休眠状態となっていた。
失業保険をもらって遊んで暮らす人が多いのである。
しかし、幼少の頃から田舎で夏はニシン漁の手伝い、冬は下駄造りと苦労を重ねてきたこともあって、冬期間仕事をしない都会のやり方に強い疑問を感じたのである。
他の地方であれば一年中働くのが基本である。
その地域は一年の半分雪に閉ざされてしまうので半分働いて半分遊ぶというのが土木・建築業界では当たり前になっていた。
それでは、自立した地域社会が形成できないと強く感じたわけである。
また、その地方では冬場三角屋根にできるつららや落雪で何人もの人の命が奪われていた。
建築という手段で社会に貢献していくことを目標にした彼は、なんとかその地域にあった独自のスタイルを確立できないかと考えていた。それは何より人命を救うためであった。
また、開拓されてから歴史の浅いその地域では東京なみの性能しかもたない建物が多かった。
冬の厳しい期間、生活者は寒く貧しい生活を強いられていた。
彼は豊かな生活はまず冬でも快適に過ごせる居住空間の整備であると強く感じた。
そのためには、匠の技で1棟1棟手造りしていたのでは間に合わない。
匠の技を活かしつつ多くの生活者に豊かな生活を提供できないものだろうかと強く感じていた。
気が付くと数え上げるときりがない程の疑問や問題が横たわっていた。
独立起業した時点でこれらの諸問題を独自に解決していくことが目的であると使命感に燃え、次々といろいろな作戦を展開していった。
立ちふさがる敵は多かった。
行政であったり、自社の社員であったり、お客様であったりと。
独自の解決策に対し、周辺の人たちが全員反対したことも多々あった。
その地域での常識を打ち破っていく訳なので無謀だとかやりすぎだとかさんざん言われ続けた。
それでも独立起業時の目的を達成するためには超えなければならないハードルなのでひたすらにクリアーし続けていった。
しかし、その都度なぜそれをやるのかということを明確に打ち出し、反対するものを説き伏せ、作戦を決行してきた。
その労力たるもの想像を絶するくらいにハードだったらしいが、敵が多ければ多いほどその思いは強くなっていったようである。
そうして、目の前に横たわる数々の問題を解決し続けて現在に至っているのである。
独立起業してからすでに半世紀、当初の基本的な問題は解決しつつあるが、新たな問題が次々と発生しており、それらの解決にむけて総勢1300名の部隊で戦っているのである。
それらの問題とは、地球の破壊が加速的に進んでいる現状をどうくい止めていくかということ。
環境破壊という言葉は日頃、目にする機会が多くなっているので新鮮なテーマではないが、確実に進行しており真面目に取り組まなければならない大きなテーマなのである。
その企業は、創業者自身が苦労を重ねてきた人なので創業当初から工夫を重ねて資源を大切にしてきた企業だった。
限りある資源を有効に活用するということは、その企業にとって常識だった。
今では、その省エネルギー生産を全面に打ち出し、その企業の社会貢献度合いを生活者にアピールしているが、今に始まったことではなかった。
資源の有効活用、匠の技による高耐久性能の維持、地域独特の生命維持装置としての住宅形態、有害物質による室内環境汚染対策、などなど。
それらは起業時に創業者が、解決したいと使命感に燃えたテーマだった。
現在では、その必要性を全面に打ち出し取り組む姿勢を見せている企業はいるが、一朝一夕にはなかなかできない企業が多い。
しかし、その企業は、半世紀にわたりやり続けていることなので見事にバランスがとれて具体的に機能・貢献しているのである。
その創業オーナーの悩みとは、他社とは違う独自のことをかたくなにやり続けている意味を正しく理解されないということである。
お客様はもちろんのこと、社員までもが正しく理解していないということらしい。
社員が正しく理解できていなくて、お客様の理解共感を得られるはずがない、という危機感からその企業の博物館の計画が始まったのである。
その博物館の概要は、創業者の家系の歴史から始まり幼少期を経て、独立起業から現在に至るまでの創業者の精神的な部分を明快に露呈し、現在の企業の理念哲学を徹底的に啓蒙しようというものになっている。
なぜ、現在その企業はそのようなスタイルでやり続けているのかという事を訴えていくのである。
総勢1300名にもなってくるとトップの理念が、現場レベルまで浸透しなくなってくるのは自然なことである。
特別なことではない。
ただし、そんな常識を打ち破るかのように創業者の初心なり哲学を末端まで伝えたいという創業者の強い想いが博物館まで創らせているのである。
経営者であり、創業者でもある私は、その仕事を通じて考えさせられることが多い。
考えさせられるというよりは、約30年先を歩く大先輩から学ぶことが、とてつもなく多いのである。
創業時の初心を実行すべく、遠く、広く、先を見て、強烈に、かつ具体的に指揮していく。
その姿はやはり1300名を動かしていく隊長にふさわしい毅然とした姿である。
わたしはひとりの設計者としてプロジェクトに参画しているに過ぎないのだが、強烈にひとりの創業者の生きざまを見せつけられると自分も毅然としなくては、と思わざるをえないのである。
本誌は、これから起業しようとしている人のサポート誌なので、自分のことはさておき、あえて言わせてもらうが、「初心忘るべからず」である。
起業すると何かと解決していかなければならないことが多くなる。
仕事を軌道に乗せることが第一優先になるが、そのことは初心を貫くための一つのハードルでしかないということ。
軌道に乗せることが目的ではないということ。
仕事が無くても初心を貫くためにやらなければならないことがたくさんあるはずである。
初心を達成するために、今何をしなければならないのかという事を常に考えて行動することが大切である。
また、起業するキッカケとなるその「初心」はどんなことでもかまわない。
ただし、基本的に社会に貢献するという初心でなければ社会から評価されないということは肝に銘じておく必要があるだろう。
積極的に、真面目に、力強く、社会貢献するという姿勢が見えなければ、社会は評価しないということ。
上っ面の建て前だけで食っていくことができるほど世間は甘くないようである。
さて、私も今一度初心に戻って、風に吹かれながら釣り糸を垂れてみようと思う。
つづく 平成9年4月 中潮
あとがき
最近、釣り糸を垂れることがめっきり減った。
不満かというとそうでもない。
「社会貢献」、「自己実現」、「環境、収入、仕事の質」と
意気込んでいたときに、この世界の大先輩を捕まえて、
「あなたは、なんのために今の仕事をしているのですか?」
とやった。
「求められるから、それに応えたいのよ!」
ときっぱり!
そんときは、しっくりこなかったけれど、
いまは、なんとなく理解できるような気がする。
しかし、枯れる前に釣り糸を垂れて、しっかりと
期待に応えたいと感じている。
2000.05.20
1986年5月、無事念願の転職を果たした。
周囲の人たちは勝手にいろいろなことを言っていた。
当時北海道にいた両親は、北海道の親戚でもわかる前企業を退職することに未練を感じていた。
ことさら母親は、せっかく大学まで行かせて、1部上場企業に勤めてやれやれと思っていた矢先のことだったので、最後までブツブツ言っていた。
しかし、新入社員当時、すぐにでも辞めてしまいそうな私を「石の上にも3年」と言ってなだめすかした本人でもあり、もうこれ以上はなだめすかせることは無理だろうと思ったらしく、最後には「好きなようにしたら」とさじを投げてしまった。
T海上に勤めていた友人は、しきりにもったいないもったいないと言っていた。
彼は、どんなにつらくても定年まで我慢しているとその先にバラ色が待っていると信じてやまなかった。
だから同じ上場企業を捨てる私に、もったいないもったいないとしきりに言っていたのである。
価値観が違っていたので、彼の言葉を聞きながら私は、「うんうん」と笑って聞き流していた。
定年までの約35年間我慢し続けるなんて考えただけでも気が遠くなりそうだったので、力説のあまり彼の口の脇に出来ていたあぶくを見ながら「ごくろうさまです」と聞き流していた。
他にもいろいろな人がそれぞれの物差しでいろいろなことを言うので、多少不安にはなった。
しかし「人の数だけ人生の数があるのだ!」と自分に言い聞かせ、自分の人生に向かって自ら一歩踏み出したのである。
それから既に11年ぐらい経過しているけれど、今のところ間違った選択ではなかったと思っている。
5月の中旬頃から、第2の修業先のT社に中途入社社員として勤務するようになった。
私の配属された部署は、その企業のなかでも特異な部署のようだった。
企業に仕えるというよりは、一匹オオカミのごとく「自分の仕事は自分でやる」と言うような人たちばかりが集まった部署のようだった。
言い換えれば、会社にとっては煙たく、組織までも乱しかねない連中だが、仕事をさせれば一流なので、会社としてもクビにするわけにもいかないという感じの仕事師集団だったらしい。
「朝9時出社ですので遅れないようにしてください」とネクタイ姿の人事部の担当に言われていた。
前企業で鍛えられていたので、朝9時出社であれば8時30分ぐらいに行けば大丈夫だろうとその日に備えていた。
当日、第一印象が大切だと思い「おはようございます」と元気よくその部署のドアを開けた。
「ん・・・・!」いない。
曜日を間違ったか。
あるいは、出社場所を間違ったか。
すぐには見当がつかなかった。
気を取り直して、出入口のところにかかっている部署名を確認した。
間違っていなかった。
石の上にも3年間、鍛えられて第1修業先を卒業してきた若者にとっては出鼻をくじかれた感じがした。
しかたなく部屋の電気を自分でつけて、入り口付近にあった打ち合わせテーブルらしきところに座って待つことにした。
待つこと15分あまりで、その部署の部長があたふたとやってきた。
「あっ!佐山君おはよう。早いねぇ」とびっくりしたようにあわてて、電気をつけようとスイッチを押した。
その日はもう私が電気をつけていたので、部屋が暗くなってしまった。
いつもは部長のH氏が一番最初に出社し、照明のスイッチを付けることになっていたのであろう。
その辺からもう既に前企業のスタイルと全く違っていた。
どちらがよいかは何ともいえないところであるが、前企業では若いのからフロアーが埋まり、最後に一番偉い営業所長が、悠々とやってくるのがおきまりだった。
そんなことに慣れてしまっていたので、その部屋で一番偉い部長が電気をつける係をやっているなんてのは、ところ変われば変わるモノだと変に感心してしまった。
しかし、なんだか自由な空気を感じていた。
「佐山君はこの席だから」と部長に案内され、席に着いた。
その部長とは中途入社面接の時から何度か会ったことがあったので気分はほぐれていた。
それから15分くらい経って、始業のチャイムが鳴った。
そのころからパラパラと何人かの社員がやってきた。
皆それぞれに抱えた難問と格闘しているのか眉間にしわを寄せながら、新人の私にちらっと目をやりながらしらん振りして通り過ぎていった。
私は、その都度背筋を伸ばしペコペコしていたが、皆が皆「あんたなんかに気を取られていたら時間がもったいないね。」ってなかんじで自分の席に着き、すぐに忙しそうに仕事を始めたので、私も邪魔しないようにしらん振りする方がいいかなと机の引き出しとかを引いたり押したり中を見たりしていた。
やることがなかったのである。
「おはよう」「ん・・・・!」不意をつかれた。
「佐山君?だよね・・」「はあ・・」
「これからよろしくな」「へ・・」
実は、配属先は聞いていたけど直属の上司の名前は聞いていなかったのである。
出社日と配属先を聞いていただけで何課の誰の下になるとまでは聞いていなかった。
「TAKENAKAです。よろしく」「さ・さやまです。よろしくお願いします」
何の形式も建て前もないのである。
その日は少なくとも同じ部署の人たちに紹介されるのかなぁと思っていたのだけどもそれは来週の月曜にするのでと言うことだった。
しきたりと長をあがめたてる形式の世界から実質と合理性に満ちた世界への急転換はかなりのカルチャーショックを受けてしまった。
しばらくしてまた「おはよう〜!」とお姉さんがやってきた。
また、「佐山君?よろしくね」「はあ・・」
「わからないことがあったら、このOさんに聞くように」とだけ言い残し、Tさんは外出してしまった。
既に朝9時45分になっていた。その時点でその課の私を含めて3人は全員顔を合わせ、それぞれの仕事へと入っていったのである。
まず、朝の全員朝礼の後、課のミーティングがあって、しこたま絞られた後、9時の始業のチャイムが鳴り「さあ仕事だ!」とケツをたたかれ続けてきた3年間とは大違いであった。
今となってはどちらが良いとは一概に言えないが、いろいろな組織を経験するという意味では、とても良かったと思う。
起業を含めて、転職するスタイルはいろいろで人それぞれ違うものだろう。
志茂田影樹のように数十回の転職の末、天職に出会い花が咲くというケースもあるだろう。
私の場合は、「大企業・給料は我慢料」から「中企業・給料は授業料天引き」と続き、「社長業・給料は社員の残りかす」すなわち大企業→中企業→自営・起業とすすんだ訳である。
ケースはそれこそ人の数だけあると思うが、私の少ない経験から判断すると、出来るだけ異なる環境を経験していた方が、後々有効になるような気がするので良いと思う。
ところ変われば全てが変わるわけであるから「定年後にバラ色の人生が待っている」と信じている方々以外は、出来るだけ多くの手の内の駒を持っていた方が力強い生き方が出来るような気がするので、その道へ突き進んだ方がよいと思う。
そこで大企業から攻めるか、その反対から攻めるかは、どの道を経験してきたかによって意見が分かれるだろうが、もしこのエッセイを就職に悩んでいる学生が読んでいたとしたら、出来るだけ大きなマンモス企業に潜り込んだ方がよいと思う。
それは、そこでしか経験できない慣習やらしきたりやらが渦巻き、人間関係や、くだらない、そこだけのやり方が掟となっている場合などがあり、とても有意義な体験が出来るからである。
かりに起業した後、一部上場の企業を相手に取引を開始することがあるとしたら、どこの部署の誰がキーマンで、どのような攻め方をすればうまく行くのかという空気を敏感に感じとることが出来ることもあるであろう。
やはり、百聞は一見にしかず、である。
手の内の駒は、多いに越したことは無いのである。
いま、私が一部上場の大企業と取引を開始するとしても、何の気後れもなく堂々と取引をすることが出来る。
それは、「我慢料」をもらいながら企業に仕えている担当者と、「社員のかす」しか給料をもらっていない社長とのハングリー度合いが大きく違っているからだ。
また、そう言い切れるのは、私には慣習もなければ建て前もなく、ただただ社会への貢献と自分の夢の実現だけで勝負にでていくという、気構えの違いがあるからだろう。
しかし、生きていくことは楽しいことである。
これからもどんどん人生を楽しんで生きていきたいのである。
つづく
平成8年4月大潮
あとがき
企業カラーというのがある。
企業の中にいると、属している集団が何色なのかさっぱり見えてこない。
しかし、外の人間からはよく見えるものだ。
正確で落ち度のない歯車を求める企業であったり、個人個人の力量に大いに期待する企業であったり。
さまざまなカラーがある。
それこそ、企業の数だけ、カラーがあるだろう。
第二の修業先は、最初の修業先のカラーとは、まったく違った。
どっちがいいかは、わからない。
しかし、企業が個人の力量を求め、それに期待し、それにむくいる、というのが、企業戦士にとっては理想だろう。
なぜならば、つぶしがきくからである。
その企業でしか通じない論理で、歯車だけを担当していると、自分で考えることができなくなってしまうからだ。
考えることは、どうしたら、減点対象にならないか、失敗しないか、そんなことばかりになるかもしれない。
人生って、歯車でもなく、失敗がつきもので、考えながら生きていかなければならないからである。
久しぶりに、このエッセイを読んで、あらためて考えさせられた。
2000.04.02
転職大作戦は、「手の内の駒の数をふやして出直してこい!」というキツ〜イ一発から始まった。
1986年5月だった。その年の3月で住宅メーカーのS社は、在職丸3年を迎えた。
いよいよ、石の上にも3年待った第一回目の転職の時期が来たのである。
将来的には、住宅設計をライフワークとしながら幅広い建築設計者として生きていきたいと考えていた私は、次の修業先を決めるにあたり、何となく毛色の変わった世界を見ておきたかった。
転職情報誌をあさった。
その時は、S社の営業マンとして車で外を飛び回っていたので誰にも邪魔をされずに車の中で情報誌に没頭することができた。
いろいろあった。大・中・小・高給・薄給・有名・無名・好条件・悪条件.......。
バブルの始まるちょうど2年ぐらい前である。
買い手市場だった。
まず最初に、『有名・小』を選んだ。
当時私のあこがれていた「渋谷東急ハンズ」をプロデュースした浜野安宏さんが率いる株式会社H商品研究所である。
ある就職情報誌に出ていた。
彼が書いた「男の存在証明」は、今読み返してもゾクゾク来る。
日本では、相変わらず男が田畑の中であくせくと働き、論理を振り回し、行動している。
しかし、男はバリ島の男たちのように静かにあぜ道に立って、日没を眺め、月を見つめて、その美しさを発見し、自然の知恵を学び自分たちが田畑で作り上げてきた『現代文明』をもう一度、じっくりと見つめる必要があるのではなかろうか。
〜中略〜
すでに何度も述べたが、石油・石炭をエネルギーとして成り立ったひとつの文明が終わろうとしている。
その文明の担い手は白人狩猟民族であり、日本人はその露払い的な存在であった。
また白人狩猟民族の便利な生産地としての役割を果たしてきた。
その過程の中で多くのものを失ってきた。
あぜ道の側に立って、今こそ男は、静かにじっくりと代案を考えるときなのである。
最もすばらしい男の存在証明ができるように.......。男の目前を素晴らしく魅力的な女が腰を振って歩いてゆく。
すごい存在で迫ってくるセックスアピール。
体の中からこみ上げてくる男のエネルギーを爆発させて、女を組み敷き、無理やり犯してしまう。
......こんなストレートな男の存在証明ができた時代は遥かなる大昔である。
今こんなことをしたら男はすぐに手錠がかかる。
男の純粋な存在証明欲求は法や常識的良心というシロモノによって完全に封じ込められてしまっている。
それでも男は男自身の力で男になるしかない。
これはそのためのいくつかの試行錯誤である。
男たちよ、たがいにゆっくりとリラックスしてがんばり直そうじゃないか!
しびれる。男でありながら、しびれないやつは男じゃないと思ってしまう。
そのくらいに田舎生まれの男の私としてはしびれてしまった。
恐る恐る震える手を押さえながら電話をかけた。
すると恐くもなんともない三島さんという担当者の声が受話器の向こうから聞こえてきた。
「就職したいんですけど。」
「では、履歴書を持ってきてください。」
「いつですか。」
「では、○月×日の△時でいいですか。」
「はっ、はい。よろしくお願いします。」
○月×日の△時に絶対遅れないように会社をさぼってしっかり出かけていった。
そこは六本木のど真ん中である。
メンズクラブで仕入れた正装で決め込んでいった。
(何てことはない、ヘビーデューティー・アイビーくずれで行ったのだが......※ヘビ・アイ〜簡単に言うと質実剛健山歩き用アイビールック)
はじめて行ったにもかかわらず、思っていた通りにカッコイイ!と思ってしまった。
そこはビルの谷間にひそかに建つ、ペンキで塗り込められた六本木の一軒家だった。
私が感じ入ったのは、その会社が六本木という街に存在するということではなくて、ペンキが幾重にも塗り込められた質素な一軒家でありながら、世の中を動かしてしまうくらいの思想が生まれているというクリエイティビティをビルの谷間で感じてしまったからなのである。
社屋に一歩踏み入れてギシギシなる床に、また感じてしまった。
「こんなところで....」
もし、訪ねていったところが六本木のとあるビルの5階でかび臭い階段室をハアハア息を弾ませて昇りながら出逢った箱ハウスだったのであれば、また人生観が変わっていたかもしれないと思う。
のだが、そうではなくて、床がギシギシなるようなペンキ・ハウスだったのでカッコイイ!と思ってしまったのである。
それは、高校生の時にポパイで垣間みたアメリカ西海岸の世界に近似していたのである。
「都市のなかでクリエイティヴなゆとりのある空間を自らの手で創造してしまう。」というポパイの世界がそこにあった。
もしかしたら浜野さんに会えるかもしれないと思いながらキョロキョロしていた。
「佐山さんですか。こちらへどうぞ。」と女性の方に案内されて会議室へ通された。
「三島です。」とすぐに担当者が入ってきた。
「ところで佐山さんは何ができますか。」
「ん.....!え〜っと!住宅の設計と現場と営業と......。」
「商業施設の経験はありますか。」
「いえ!これから経験を積んでみたいと思っています!」
「うちは少数精鋭でやっているので未経験者を教育している余裕がないんですよ。もう少し別のところでいろいろと経験して手の内の駒を増やして出直して来てください。では。」
「ん.......¨;」
がーん!と一発、言い放たれあっけなく終わってしまった。
しばらく六本木の街の中をうろうろしながら「手の内の駒...手の内の駒....」と頭の中で言葉だけがぐるぐる回っていた。
今までの経験だけでは、通用しないのだろうか。
やる気があるだけでは、通用しないのだろうか。
意味もなく雑踏の中を行ったり来たりしていた。
気を取り直して、次のトライが始まった。
『小』では、未経験者を教育する余裕はないのかもしれないと思い『中』をねらってみた。
そんな中、『小・高給』と『中・薄給』の商業施設系企業が目に止まった。
まずは、『小・高給』から攻めてみた。
また、なぜか六本木だった。
「手の内の駒」の経験があったのでダメでもともと電話をしてみた。
履歴書を持ってきてくださいとのことだった。
行くとまたペンキハウスの一軒家だった。
なぜか六本木の設計事務所はペンキハウスが流行りらしかった。
しかし、そこは前回ほどワクワクするものが無くむなしいただの貧しい一軒家に見えた。
そこは担当者ではなくて、社長の M氏が直接面接してきた。
こちらとしては、「手の内の駒」事件から日も浅かったせいもあり、多少のことでは動じないくらいに腹が据わっていた。
そんなこともあり、面接の時に40歳くらいの社長を相手に「あなたの将来展望は?」なんてやってしまった。
そんな私の堂々としたふてぶてしさが気に入られたらしく、すぐにM社長の将来展望やら私の将来構想やらの話で話が盛り上がってしまった。
「また、こちらから連絡するよ。」といわれペンキハウスを出て六本木の街に出た。
しかし、なぜかほんの5分ぐらい前に盛り上がっていた内容よりも「手の内の駒...手の内の駒....」とまた例の言葉が頭の中でぐるぐる回っていた。
街の雑踏の中で「手の内の駒...手の内の駒....」とぶつぶつ言いながら日比谷線に乗り、電車の中でも目は宙を舞い念仏のように「手の内の駒...手の内の駒....」とやっていた。
次は、『中・薄給』の企業の面接だった。
その企業は大学4年の時に会社説明会に出席したことがある企業だった。
その時の説明会の担当者は何となく暗くあまり全体的にいいイメージを持たなかったのでそれっきりでアプローチしていなかった。
しかし、中途入社募集、若手歓迎とあったので、もしかしたら中規模の企業であれば未経験者の私でも修行させてくれるかもしれないと思い再度訪ねてみることにした。
場所は上野で有名な人が居るわけでもなく何のワクワクすることもなく自然体で出かけていった。
しかし、大学時代からその筋ではトップ企業と知っていたので、ある程度の期待はあった。
その期待とは、自分の修業先として充分かどうかということなのだが。
訪ねてみると、学生時代に会社説明会で受けた印象やそれまで面接を受けてきた『小』とは違い会社全体にざわざわとした活気があり、なぜか気持ちが良かった。
よくよくその企業の説明を聞いてみると種々雑多な業務を日常業務としてやっていることがわかった。
建築設計、インテリア設計、マーケティング、商業施設、文化施設、リゾート開発、地域開発、何でも屋だった。
私は、その何でも屋がえらく気に入ってしまった。
そして、なんだか全体的にざわざわしている活気も好印象だった。
「また、連絡します。」と言われ上野の雑踏に意気揚々と出ていった。
そして、またしても「手の内の駒...手の内の駒....」とぶつぶつやっていた。
しかし、六本木のぶつぶつとは明らかに違い、空を見ながら胸を張り「手の内の駒...手の内の駒....」とやっていたのだった。
少しだけ悩んだ。
『小・高給』と『中・薄給』。
当時、25歳で妻がある身としては、『高給』は捨てがたかった。
子供でも生まれようものなら自分の夢や修行を続けられなくなると思い、少しだけ悩んだ。
妻は悩まず『高給』に目が釘付けだった。
しかし、『小・高給』のM社長は、私にパートナーとしての期待をしてきていた。
初回の面接から息があってその後何度か面接を繰り返したのだったが、会う度に私に過度の期待をしているようだった。
私としては、うれしくもあり期待に添える自信は十分にあったのだが、「手の内の駒」を増やすという意味では心細かった。
その社長一人からノウハウを吸収してしまったら終わりなのである。
駒がひとつだけでは、不安だった。
30歳までに3回の転職を重ね、建築の世界に挑もうとしている若者にとっては、手の内にする駒は多すぎて困るということはないと思いこんでいた。
『中・薄給』の企業は、その点申し分無かった。自分を試すフィールドは限りなく無限に見えてしまっていた。
少しだけ悩んで、すぐに結論が出た。
『中・薄給』からも強力なアプローチがあり迷わず『中・薄給』に転職することに決めたのである。
妻は、少しだけがっかりしたものの私の将来的可能性に賭けてくれてひとまず納得してくれたのだった。
そうして、1986年5月に転職を決行した。
前職を退職するにあたりかなりの引き止めがあった。
しかし、石の上にも3年待った上での結論である。
自分の意志に揺らぎはなかった。
新たなる修行への旅立ちなのである。
さわやかに慰留を断り続けた。
やめる直前に私が仕掛けていた一軒の住宅の契約が他の社員の手柄となった。
その歩合給は約30万円程だったが、「いいですよ。いいですよ。」と何の未練もなくさわやかにその社員に渡してその企業での修行は幕を閉じた。
そしてまた、「手の内の駒...手の内の駒....」と意気揚々にして2社目のT社へと転職していった。
転職してみると『大・高給』と『中・薄給』は大違いのことが多くかなりのカルチャーショックを受けてしまった。
つづく
平成8年 3月 若潮
あとがき
今から14年前の話しだ。
期待通りにT社では、いろいろな修行をさせてもらった。
結局、3年程度で転職しようと思っていたのだが、8年ほども修行させてもらった。
結果、多くの手の内の駒を仕入れることができて、今の生活空間研究所があるのだ。
新入社員からの3年間は、住宅産業とはなんぞやを学び、その後の8年間は、世の中の流行や財布の紐をゆるませる手法はどのようにして、というのを学んだ。
どれも大きな財産になっている。
2回目の転職はせず、10年強修行を積んだところで、自分で会社を作ってしまった。
すこし、人生設計の軌道はずれたけど、これでいいのだ。
2000.01.31
前回のエッセイは転職大作戦が始まったところで「つづく」だったが、今回はその続きではなくて勝手に近況報告に変更してしまうのであしからず。
ただし、それよりもたぶん面白い話になりそうなのでここで止めずに読んでみていただきたい。
このエッセイは風に吹かれるようにテーマも何もなくただその時思うことを書こうと決めたエッセイなのでこれでいいのだと勝手に私は思っている。
従って、誰も止めることはできないのである。それでいいのだ。
私は、平成5年4月に今の会社を設立した。
さかのぼると平成4年10月に前職のT社を辞めた。
T社を辞めたきっかけは、それはもう単純明快、動機不純、それでいいのかと普通の人であれば思うくらいちょっとしたきっかけだった。
T社に勤めいてたその頃、「自分の顔で仕事がしてみたい」とか「一生懸命やればやるほど自分が豊かになっていくより会社が豊かになっていくのではないか」と日々思い始めていた。
その悶々とした思いは、電車に乗り、人の波に飲まれていく毎日で次第に大きくなっていった。
「T社を辞めて、自分の顔で仕事がしてみたいな。」
「いつまでこの納得のいかない繰り返しを続けるんだろう?」
「このままでいいんだろうか?」
とぐずぐずしているときになんとまあリストラがあったのである。
その時、実はリストラがないまま退職しても退職金で返済しきれないほどの借金を会社にしていたのである。
朗報だった。
計算するとリストラの波に乗り会社を辞めると借金を返済できるどころか、かなりのおつりが来るらしいことがわかった。
そうなるとイケ!イケ!である。
元来、楽天的な私としてはもうそれだけでモーゼのジュッカイのように未来への道が開けたような気がしてしまっていたのである。
すぐに手を挙げていた。
でも、そのあとどのようにして生計を立てて行くかの見通しはな〜んにも考えていなかった。それよりも借金を返済してなおかつおつりが来るというプラスからのスタートということが精神的に大きな支えとなっていた。
しかし、そのプラスもすぐに底をつくのは目に見えていた。
どうせ無くなるものなら、形にしておきたいと全財産を持って秋葉原を歩いていた。
今から3年前である。財布に入りきれないぐらいの万札を持って、マッキントッシュを買いに行ったのである。
平成4年の暮れだった。
もうすでに街は年末商戦真っ盛りでみんなギラギラしながらパソコンをあさっていた。
気後れしながらもこのチャンス(お金を持っているチャンスという意味)を逃すものかという意気込みでわけも分からず秋葉原を歩いていた。
その時点で自分が納得できるマックに出会えたような気がしたので迷うこともなく全財産をはたいて意気揚々として家路についた。
年賀状をつくってみたいと思ったのでそれからすぐに格闘したが、年が明けて3日になっても思うようにいかないのでその年はイモバンでことを済ませることにしてしまった。
それはそれでいいのである、年賀状をつくりたくてマックを買ったのではないのであるから。
しかし、そんな無謀とも言える投資をしたおかげで今ではしっかりとマルチメディアの恩恵を受けることができているのである。
ちなみに私の事務所には製図板がひとつもないのである。
そのかわりにマックが3台常にフル稼働している。
来月からはもう1台増えて4台のマックでデザインに格闘することになっている。
話は戻るが、会社を辞めてしばらく失業保険をもらう身に身をゆだねていた。
その期間、私は定職についてはいけないのである。
職安からきつくそう言われていた。
仕事をしてはいけないことをいいことに自ら仕事に就かなかった。
(企業に就職しないということであるが.......)
それは、楽しかった。
定職についていないのである。
朝、9時までに決まったところに働きに行く必要もなかったうえに、サラリーマンのように決まったときに給料のごとく失業保険がもらえるのである。
それはもういいことずくめだった。
毎日、思うがままに日々を過ごし、思う存分人間らしさを充電していた。
知りたいことがあれば、一日中図書館に行き、白菜が豊作だと知れば漬け物を漬け、あそこに温泉ができたと知ればそこに行き、雨ニモマケズ、風ニモマケズ状態だったのである。
その期間は、約6カ月だった。
6カ月もそのような状態がつづくともう元には戻れないのである。
本来の人間に戻ったしまったのである。もう11年間続けた企業人には戻れないことを確信していた。
「そんじゃあ、人間らしく生きながら自分の顔で仕事をしていこう!」と会社を創ることにしてしまった。
会社を創るといっても最初から仕事なんて来るかどうかさっぱりわからなかった。
社員は私一人だった。
自分の喰う分だけだったら何とかなるような気がしていたのでさっさと創ってしまった。
本社所在地は、いろいろ検討した結果、自然が豊富な田舎で、都心にも気軽に出かけられ、ある程度の文化的な香りのするところという基準で現在の神奈川県葉山町を選んだ。
というのは建て前で本音は、いつでも釣りに出かけられるところが第一条件だったので葉山に決めたのである。
案の定、創立した当初は仕事なんてほとんどなく、毎日毎日夕方になると近くのポイントに竿を持って出かけていた。
将来の不安は多少あったが、そのうち忙しくなったらこんなことはしていられないんだと思い、せっせと磯場に通っていた。
(おかげさまで、いまではほとんど釣りに出かける余裕もなく日々を忙しく消化しているだけなのだが。)
創業2年目の昨年の夏、「鬼退治に私も連れていってください。アルバイトでも結構です。」という青年が突如現れた。
その時たまたま締め切りが目前に迫っている物件がいくつかあり、猫の手も借りたい状況だったので「マックを使って図面を描けるのであれば、一緒に鬼退治に行こう。」と私は答えた。
「パソコンは使ったことがありませんが、使ってみたいと思っています。」
「であれば、マックを一式そろえて自宅に置いて自分で特訓する覚悟があるのなら考えよう。」
「わかりました。すぐにそろえてお供したいと思います。」と言うわけでアルバイトながら一人社員が増えることになった。
そうこうしている内に二人だけでは、いくらやってもこなせなくなる様な状況になってきたので「きび団子はいっぱいあげられないけれども俺と一緒に鬼退治に行ってくれないか。」とT社の元部下に声をかけた。
「考えてみます。」と言って6カ月ほどが過ぎた。
「鬼退治には、お供がたくさん必要です。いずれたくさんのお供を引き連れて鬼退治にいけるように頑張りますので私にもお供させてください。」という返事が返ってきた。
「よし、それでは3人で力を合わせて鬼退治に行こう!」ということになった。
しかし、本社である事務所は、社長、兼雑用係、兼運転手である私の一人仕様になっていたので、社員規模拡大による本社移転の必要に迫られたのであった。
半年ぐらい前から、そんなことを予測していたのでひまを見つけては物件をあさっていた。
葉山に本社を決めたときのように自分なりに納得のいく基準を設けていた。中途半端なところで妥協することだけはしたくなかった。
移転先は、やはり葉山近辺で自然が豊富なところ、海のすぐそばか、山の中のどちらか。
普通のオフィスビルのような箱はダメ、わらぶき屋根の民家か、歴史のある一軒家。
一般的な本社の移転先を決める基準とはまるで違うと思うが、それが自分らしさなのだと思い込み探して歩いた。
思いのほか、葉山近辺はそんな不思議な基準を満たす物件がぞろぞろあるのである。
しかし、不動産屋にはなかなか出てこない。自分の足で探すしかないのである。
江戸時代の徳川藩の屋敷跡、化け猫で有名な鍋島藩の屋敷跡(本当に大きな古井戸があるのである)、
帝国ホテルを設計した有名なアメリカの建築家ライトの弟子が設計した住宅。
アントニン・レーモンドという日本の建築史に残る著名な建築家が設計した別荘。
売り物件が多いが、よだれのでそうな物件がぞろぞろあった。
なかでも圧巻は、葉山の御用邸を後ろにしながら山道を上がっていくとあるログハウス群が私の心をとらえてはなさなかった。
ログハウス群とは言ってもそのオーナーが自分の手で時間をかけてつくりあげた質素な建物群なのであるが、そこから見えるパノラミックな眺望が何ともすばらしいのである。
御用邸の前の国道からものの10分程の山の中腹にへばりつくその敷地は私にとってこの上もない楽園に見えた。
しかも、全て自分の手作りで仕上げたであろうと思われるその楽園は私のめざす生き方の手本になっているように感じられた。
あえて例えるならば「大草原の小さな家」の葉山版である。
物件探しがてら散歩している途中で偶然見つけてしまったその「大草原の小さな家」は、寝てもさめても私の脳裏に焼き付いたまま離れることがなかった。
そうこうしている内にいよいよ真剣に本社移転を検討しなければならない時期がやってきた。
いろいろ他にも検討していたが、どうしてもその「大草原の小さな家」が気になり、ダメでもともと直接オーナーにアタックしてみることにした。
突然の訪問で不信がられないように正装で決め込み、山道を上がっていった。
そして自分のことを正しく理解してもらえるようにと会社と個人のプロフィールもしっかりと持っていった。
どきどきしながらチャイムを鳴らした。
「ピンポン〜」
「ハ〜イ!」......「ん?」
「ナンデスカ?」......「ん?」
帽子をかぶり、赤いチェックのシャツにジーパン姿のまるで絵に描いたようなアメリカ人のおじいちゃんが出てきたのである。
「ここの場所がとても気に入りました。よろしければ私に貸してもらえないでしょうか。」
「考えていません。前に他人に貸したときにうまく行かなかったので可能性はないでしょう。」といわれてしまった。
まあ断られてもしかたないと思っていたのでさほどがっかりもせず、「まあ私のプロフィールでも時間があったら読んでみてください。」と用意してあったものを手渡し、やっぱりダメだったかと山を下りた。
まあ、やるだけやったので後悔はしていなかった。
しょうがない、次を探すかと思っていた矢先、訪問してから1週間ほどたってそのおじいちゃんから電話があった。
一軒貸してもいいと思う小屋があるので見に来ないかという電話だった。
いくらで貸してくれるかわからなかったので不安はあったがとにかく行ってみることにした。
電話を切るとすぐ、ににたにたしながら山道をかけのぼっていた。
おじいちゃんからその小屋の説明を聞きながら、ますますそのロケーションの虜になってしまっていた。
さらににたにたしながら、条件を確認したところこちらの思っていた条件よりもかなりよい条件が提示された。
足元を見られないようにせねばと思い「きっ!」としていたつもりだったが、顔はにたにた、でれでれ状態でしっかりとコーヒーをごちそうになっていた。
前々回の本誌にも書いたことだが、思いを強く持ち、それを実現するためには何をするべきか真剣に考えかつ行動すると本当に実現するようである。
そんなわけで、3月に本社移転をすることになった。
それは、自分らしさ、社風、ライフスタイルをみごとに表現できる場所への移転なので今からとても楽しみである。
一緒に鬼退治に行く他の二人もそれはもうとても楽しみにしてくれている。
なぜならば、富士山、江ノ島、大島、湘南の海原が事務所から一望なので最高の職場環境だからである。
このエッセイを読んで是非一度訪ねてみたいと思った方は、いつでも来ていただきたい。仕事のことなんか忘れて、自然を一緒に楽しみましょう。
そして、一緒に自分らしさとはなにかを考えましょう。では。
平成8年 3月 中潮
あとがき
創業当初の仕事を増やし何でもかんでも突き進むことが目的の時期の話しである。
今から五年ほど前になる。
当時は、真剣に千人ぐらい社員がいる設計事務所にしようと考えていた。
その後7人ほどにまで増やしていったのだが、その時点で仕事と私の性格から社員を増やすことにメリットを感じなくなっていった。
私は、本エッセイにあるように会社の看板で仕事をするのではなく、自分の能力やノウハウで仕事をしていきたいという思いからサラリーマンをやめたのである。
社員を7人程にしたときに、仕事と社員を増やすことは、私の顔で仕事をしていきたいという初心がどんどん薄れていくことにつながることに気がついた。
そして、以前私がいやと感じた、滅私状態で私の顔を維持することを社員に強要するのもどうかと思い始めたのだ。
それで、社員が卒業していくことを拒まず、増やすこともせず今に至っている。
独立してから7年目を迎える今、初心に戻り最小単位に戻り、SOHO (Small office ,Home Office)と決め込んだ。
夢のような「海一望、山の中」のログハウス・オフィスは、平成7年から平成11年春まで、計4年ほど住み着いていた。
本分に出てくるアメリカ人のおじいさんは、顔を合わせると決まって「ショウバイ、ドウ?」と聞いてきたものだ。
彼も50年近く、商売をやりながら、ログハウスを造ったり、いろいろなことをしてきている。
生き方や考え方などは、やはり私の大先生だったのである。
多くのことを教わった。
「オイチョ、カブ、ヤッテルカ?」と何度も繰り返す意味が最初分からず、ゴールドラッシュを舞台にした映画を見て納得した。
社員にどんどん給料をやって、働かせるだけ働かせて、ばくちで巻き上げるのが、腕の立つ経営者というものらしい。
そんな敏腕経営者になりたくて独立したわけではないので、平成11年の春からSOHOということにしたのだった。
2000.01.07
1986年、社会人になって4年目。
石の上にも3年たった。
社会人1年生の頃は、つらく長い日々と感じただけだったが、2年目、3年目の頃は、つらい中でも仕事のおもしろさが少しだけわかりかけてきていた。
そして知らず知らずの内に多くのことを学んでいった。
その住宅メーカーで最初に担当した仕事は、現場監理であった。6カ月程度の新入社員研修の後、いきなり3棟の現場を任された。
正直なところ、現場に出ても全てが初体験で何をどうしてよいのやらさっぱりわからなかった。
先輩社員の様子をうかがいながら見よう見まねで何とかしのいでいた。
わからないことだらけだったので、お客に会うのがとてもこわかった。
現場でいろいろなことを聞かれる。
わかった振りで乗り切れることなら何とかごまかせるが、わからないことは「後で調べてご連絡します。」と言うのが精いっぱいだった。
そんな中、やっぱりお客の感情が爆発した。
知らないことだらけで何とか乗り切って、1件の住宅を引き渡す日が来た。
出来上がった住宅の中で、竣工検査や書類の受け渡しなどの儀式を行っている最中、お客の顔が青ざめたのである。
そして、突然しくしく泣き出した。
今でも鮮明に覚えている。
40歳ぐらいの公務員のかただった。
大の大人が突然泣き出したのである。
びっくりした。
「自分は、家を建てるのが初めてである。お宅のような一流企業だから大丈夫だと思っていたけども、やっぱり担当者を換えてもらえばよかった。」と言いだした。
担当者とは、私のことである。
何故、急にそんなことを言い出すのかと内心首をかしげていた。
「最終打ち合わせの時に頼んでおいたコンセントが3つ付いていない。」と言うのである。
そばにいた営業担当は「すぐに追加工事としてやらせますから、大丈夫です。」とあわててその場をとりつくろうとしたが、一度切れたお客の感情はなかなかすぐには戻らない。
公務員として少ない給料をため続けてやっと家を建てるにいたった苦労話をしばらく聞かされた。
私は、その3つのコンセントは壁の下地の中に埋め込まれているのをチェックしていた。
ただ、壁の表面に器具として付けるのを忘れていただけなのである。
しかし、監理不行き届きで最終チェックを怠ってしまった私のミスであることには変わりなかった。
私は、申し訳ない気持ちでいっぱいになり、黙って下を向いていた。
この事件は、学生気分のまだ残っていた私の気持ちにカツを入れてくれた。
こちらにとっては、数ある中の一つの現場でしかないが、お客様にとっては一生に一度あるかないかの大事業なのである。
頭ではわかっているつもりだったが、初めて身をもって知らされた。
また、青二才の1年生でも給料をもらってやっている以上、プロとして仕事に望まなければならないことも学んだ。
それは、現場で大工がトントンやっているそばで図面の通り施工されているかチェックしていた時だった。
その日、「おはようございます。」と声をかけて現場に入っていったのだが、大工は新米の私には目もくれずトントンとやっていた。
「ふん、おまえなんかよりずっと長いこと現場でやっているんだ。指示なんか受けるもんか!チェッ!」とでも言いたそうにその大工は私のことを知ってて知らん顔していた。
大工の気を曲げるとやっかいになりそうだと思い、愛想を振りまきながら図面と現場を見比べていた。
その時、一つの窓が気になった。窓がどうもまっすぐ付いていないような気がしたのである。
「親父さん、私の見間違いかもしれないけど、この窓まっすぐに付いていないような気がするのだけどなぁ.....」
「まっすぐだよ!」
「う〜ん......」
「まっすぐだってば!」
「う〜ん.....そうかなぁ」
その親父は、それ以上めんどくさそうにして取り合うのを露骨に嫌っていた。
しかたなく「水糸を垂らしてみるよ。」と言って、知らん顔している親父を横目に窓の上部から水糸を垂らした。
1・50・ぐらいある窓の下端で1・窓が傾いていた。
「親父さん、鉛筆の芯一本狂っていたから後で見ておいてくれない?」
「そうか、鉛筆の芯一本か。う〜ん......あんたみたいな人は初めてだ。鉛筆の芯一本の狂いを指摘するのは。」
その瞬間から、その親父の私に対する態度ががらっと変わった。
他の監督は、そのくらいの狂いは見てみない振りをするのだそうだ。
まあ大勢に影響はないから問題ないのだが、そこまでチェックするのは珍しいとのことだった。
後から考えると、その親父はそのくらいの狂いはわかっていて、私を試したのかもしれない。
なぜなら、その親父の試験にパスしたためか、それ以来、新米の私の指摘でも快く引き受けてくれるようになり、その親父さんの現場はスムーズに運ぶようになっていったからである。
その時、新米であることに気後れして追求していなかったら、その後もずっと相手にしてもらえなかったかもしれない。
現場監理を約1年担当したあたりで、なぜか私に営業的センスがあると感じた上司は私を営業の部署に推薦したため、営業をやることになった。
目標ではあと1年ほどで次の修行の場に出る(転職)予定でいたので、できるだけいろいろ経験しておくことも必要だと思い人事異動に素直に応じた。
結構、面白かった。
私の所属した課の上司は、殴る蹴るの体育会的きびしさで有名だったが、営業のセンスは職人芸だった。
その上司は、私が営業とは畑違いの建築出身だったためか他の課員とは違い手とり足とり営業の極意を指導してくれた。
「客の真意は、話していることと反対だと思え。」といつも言われた。
つまり、「いいわねぇ」と言われたら「いいけれども、もっといいのがあるのよ」と解釈する。
「今すぐじゃないからまた今度にしてくれる。」と言う客に限って、他の業者と商談している場合が多く、言葉を鵜呑みにしてしばらくしていくと「いや、もう決めちゃったから」なんてことになるものだと教えられた。
また、「質問には質問で答えろ。」とも指導された。
たとえば、「おたくは高いんじゃないの?」には、高くない説明をする前に「どのくらいで検討されているのですか?」と切り返し、「まだはっきりしていないから。」には、「いつ頃のご予定ですか?」とにかく考えつく限りの質問で会話を進めていくと相手の本音がぽろりと出てくるということである。
人間関係ができていない初対面の頃に激しくそれをやると怒鳴られることもあるが、人間関係ができてくると結構本音が聞き出せるものだと感心していた。
これは、テクニックであると思った。
設計畑では、教えてもらえない営業のテクニックである。
他にもいろいろなテクニックがあって、他では得難い私の貴重な財産になっている。
また、その営業所では、営業がお客様と折衝するために営業が自分で住宅のプランをつくることになっていた。
当然私は、建築出身なので得意とするところであるが、私の上司はその道20年も歩んできた芸人なのでプランをつくる上でも学ぶことが多かった。
プランをつくる上で特に感心したのは、建築予定地を調査しに行ったときである。
技術系の社員と一緒に行って平板測量をやるのであるが、測量が終わって技術系社員が道具を片づけている時にプカ〜ッとたばこをくゆらせながら敷地の真ん中で目をつぶっているのである。
測量が終わっているのでもう調査は済んでいるはずなのだが、動こうとしないのである。
しばらくしておもむろに近隣一帯をネズミのように短い手足をめいっぱい動かしながらちょこちょこ動き回り調べ始めた。
呆気にとられて黙ってみていた。
その課長と現地調査に行くといつもそうするので、何度目かの時に聞いてみた。
「プランは、机の上でするものじゃないよ。」と言われた。
つまり、敷地の真ん中にたって、頭の中でプランを検討し、その家の中で生活している様子を頭の中でシミュレーションするのだそうだ。
その時に、風の流れや聞こえてくる音にも神経を集中するのだそうだ。
そして、敷地から見えるもの近隣から見える敷地の様子をちょこちょこ動き回りチェックするのだそうだ。
圧巻は、近隣を動き回り、その筋の人がいないかどうかというのも忘れずに見て回るとのことだった。
その筋の人がいると工事中にトラブル可能性があるので慎重に予算を組まなければならないというのである。絶対に学校では教えてくれない職人技である。
学ぶことが多く、社会経験的には充実した日々を送っていた。
そして、石の上にも3年目の日々が過ぎた頃、いよいよ転職先を具体的に検討し始めた。
3年所属したその企業では、収入はそこそこよかったが、仕事の質と職場環境に疑問を感じていた。
私は、働く環境の要素は、大きく3つに分けて考えることにしている。
仕事の質・職場環境・収入の3つである。
質とは、言うまでもなくやっている仕事内容であり、自分の目標に近づくことのできるクオリティを有しているかどうかということ。
職場環境とは、人間関係、企業慣習などの点で自分がのびのびと仕事できる環境かどうかということ。
収入は、その年齢に見合った収入が得られるかどうかということ。
これらの3要素が整いさえすれば、今でも自分が経営者であろうが、サラリーマンであろうがどちらでもかまわないと思っている。
逆に3つとも揃わないようであれば、迷わず転職・転業した方がよい。
そんな中ではよい仕事などできるはずがないからである。
その時は、全てにおいて満足できる状況に身を置くことは理想であるが、ある程度割り切って、全てを望まないことにした。
3つの内ひとつだけでは長続きしないと思ったので、最低2つを満足させられる修業先を探すことにした。
収入で前企業を上回ることのできる企業はなさそうだったので、迷わず質と職場環境で転職先を探すことにした。
そうして、私の転職先探し大作戦が始まった。
つづく
平成8年 2月 中潮
あとがき
若い頃の苦労はかってでもしろとよくいう。
あとからいい意味で肥やしになるのである。
社会人成り立ての頃はつらくてつらくて仕方がなかった。
自分の歩く道ではないといううぬぼれた思いが強いため苦しんだ。
今となっては、いい経験をさせてもらったと思っている。
はなしの中にでてくるY課長は今では偉くなり営業所長をやっていると聞く。
今でも強烈な個性を発揮しているであろうが、当時はとても強烈だった。
しかし、新年の挨拶に課員と家に行くと子煩悩なお父さんで会社にいるときとは違う人間に思えた。
ただ、そのかわいいおぼっちゃまが、大きな声で「おおきく〜ひろが〜る、ゆめ〜ゆめ〜ゆめ〜」と歌うのにはまいった。
やはり、生きる水が違うとひそかに思ってしまった。
また、その会社の男性社員は毎日とても遅くまで働いているので、晩御飯を家族と食べないのだ。
その後、いろいろと社会経験を積むうち、上場企業はそういうものなのだと知った。
晩御飯は家族で食べるものという環境で育った私は理解できなかった。
そんななんやかんやで転職を真剣に考えるようになっていったのである。
1999.11.02
このエッセイも、はや8回目を迎えた。
いつも締め切りは、月末の25日と決められている。
この25日がなかなか守れない。
守ったのは、最初の第一回目の時だけだった。
そのときは気合いが入っていた。
「佐山さん頼むよ。」と約一年ぐらい前に言われたときから何を書こうかと考えていたのだから、それはもう気合いが入っていたのである。
しかし、2回目以降は書いてほっとしたとたんにすぐ25日がやってくるので困っているのである。
サラリーマン時代は、25日の給料日が待ち遠しくて今か今かと財布の中身と相談していたものだったが、そのときとは時間の進み方が違うようだ。
という言い訳じみたことを書いてしまったが、今はもう既に1996年を迎えてしまっているのだ。
(編集部の茅原さん関係者各位殿いつも遅れてすみません。)
これが発行されている頃はもう2月になりかかろうとしている頃なので読んでいる方は、何を今更と思うだろうが、まあ元日に戻ったような気で読んでいただきたい。
大学生から社会人になって間もない頃「もうこのままずっと働き続けなければならないのだろうか」と心の中でじたばたしていた。
前回のエッセイに書いたことだが、一生大きな企業の歯車として忠誠を尽くすのもなんとなくいやだった。
そんなわがままな状況で自分を納得させることができたのが、職業人としての目標だった。
20代は修行、30代は修行と貢献、40代は貢献、50代は何もしない。
悶々としている状況の中で、もがき苦しみながら出した結論だった。
苦しみ抜いて出した結論だったおかげで、今でも忘れずに心の引き出しにどっかと居座っている。
社会人3年生にもなった頃、この結論とも目標とも夢とも言えない計画を誰かに話してみたくて大学時代所属していた研究室の初見学先生を訪ねてみた。
「私は、20代は何をやっても修業の時代だと思うんです。ですから、建築を職業として選んだ以上は、20代のうちにしっかり修行をしておきたいと思っています。」
「........」
「そのために30歳を迎えるころまで少なくとも3年ずつ3つの企業で職能を吸収し、手の内の駒を増やしたいと思っているのです。そして30歳以降はじっくりと建築に取り組みたいと思っています。」
「........」
「そして、50歳で現役を引退し、山の中に入り悠々自適に生活を楽しみたいと思っています。」
「う〜ん.....君らしいな!」
「ただし、3年ずつ3回修行というのはどうかな?人間年齢とともに記憶力も吸収力も衰えていくものだから3年5年7年、いや3年7年11年の修行かもしれないな。」と久しぶりの酒を酌み交わしつつアドバイスを受けた。
なるほどなとは思ったものの、3年7年11年だとすると修行のまま50歳になってしまい、自分の立てた計画からはずれてしまうのである。
やはり、50歳からは自然の中で遊んで暮らしたいと思ったのである。
そんな会話から8年後の一昨年のことである。
また、初見先生と久しぶりに飲む機会があった。
「どうしてる。」「いや〜、人生いろいろありますね。」と照れながら近況を報告した。
それまでの仕事のこと、家庭のこと(私の一回目の結婚の媒酌人だったのである。)などなど。
そして、「設計事務所を葉山に構えることにしました。」と報告する。
「う〜ん、そうか.......やられたな。」
「えっ!なんですかそれは。」
「いやね、ぼくもいつか海に向かって開放された書斎で仕事をしたいと思っているんだよ。海に向いた5、6mぐらいはある長い机の上にいくつものやりかけの仕事をそれぞれに置いて、必要に応じて場所を移動するだけで違う仕事ができるような環境をつくりたいと思っているんだよ。」
「やればいいじゃないですか。」
「いま、少しずつ準備をしているんだが、先を越されてしまったな。ははは」私の尊敬する初見先生は、かつて東大のヨット部に所属していて私の事務所のある一色海岸あたりは若い頃よく通っていたということで、大変うらやましそうにしていたのである。
よく考えてみると私は、大学卒業後最初の企業で3年、次の企業で7年半、そして今に至っているわけで奇しくも初見先生が言っていた3年7年11年の軌道に乗ってしまっているのである。
その言葉を気にしていたわけではなかった。
たまたま、2つ目の修行場だった企業が、とても面白くいろいろな修行ができたのでついつい長居してしまっただけだったのだが。
そして、3つ目の修行場は自分でつくってしまった。
さらに、50歳になったら自然の中でというのが待ちきれず職業計画とは別にもう既に自然の近場で暮らし始めている。
計画は、どんどん狂っていっているけれど目標にはどんどん近づいていっている。
やはり、自分がやりたいこと、したいこと、をはっきりさせることは有意義なことのようだ。
それもより具体的に、よりビジュアルにイメージすることが良いようだ。
私が、3年前に企業人から職業人(簡単に言うと企業人とは職能を企業に求める人、職業人とは職能を仕事に求める人。)に転向したときも、節目として職業人としての初心を整理してみた。
それは、建築設計を生業とする職業人として個のキャラクターをさらけ出し、「こんな自分だが私はこう考える」というものになった。
1;私は、いろいろな生活が大好きです。生活は訓読みで「いきいき」と読みます。
いきいきとした生活のための空間をつくりたいと考えます。
そのためにまずは自分の生活を楽しむことを努力したいと考えます。
2;私は田舎が大好きです。
自然と共棲しながら無理なく生活を営むことができる田舎が大好きなのです。
3;私は釣りが大好きです。
一日無心になって外で遊び、嫌なことは全部忘れることができるからです。
4;私はお酒が大好きです。
使い方にもよりますが、イメージトレーニング、コミュニケーションツールとしては有効です。
5;私は楽天家です。
信念を持って「なんとかなるさ」で頑張ることが信条です。
6;私は地球と仲良くつきあっていきたいと思っています。
人間を含めた生物の健康と地球の健康を新しいやり方で模索していきたいと思っています。
7;私は施主と社会の利益を守り発展させることが職能と考えます。
音楽家は聞く人に夢と希望を与えます。
小説家は人間とはなにかを訴えます。
冒険家は人間の限界と勇気を教えてくれます。
皆、生きざまをさらけ出して訴えてきます。
建築家も自分の生きざまや生活をもって人間と地球の豊かさを追求し、施主と社会の財産を守り発展させていくことが職能であると考えます。
生涯の目標、10年スパンぐらいの中期の目標、1年ごとの目標、月間目標、週間目標、その日の目標。
スパンが短くなればなるほど、現実的で処理しなければならないことに近い意味になる。
生涯の目標や中期的な目標があって日々の目的も見えてくるような気がする。
また、長期の目標がより具体的であればあるほど現実になる確率が高くなるとも思う。
と言うわけで私も1996年を迎え今年の目標を立ててみた。
それは、「頑張らない!」という目標である。
これは新聞に載った丸紅の鳥海社長の年頭の挨拶から拝借したのだが、「頑張ろうと思うと本来まじめな日本人はプレッシャーがかかり、かえって実力を発揮できない場合が多い。あなた方は、プロなのだから自分の仕事をエンジョイしながらやりなさい。」ということらしい。
昨年、私もふとそう感じるときが頻繁にあった。
スケジュールが迫ってきてやらなければならないことが重なってくると本来の仕事の意味が見えなくなってしまい、ついつい処理することに終始し始めるのである。
どんどん視野が狭くなり、愚痴が多くなり、自分の無能さが気になり出すのである。
そんな時はもう生涯の目標や生活を楽しむことなど忘れてしまっている場合が多い。
楽しんでいないのである。
それは、きっと仕事にも現れているのだろうと思うと依頼主に申し訳ない気持ちでいっぱいになってくる。
そんな時は、海に出て頭を上げて遠くを見るようにした。
本当に忙しいときは、歩いて1分ぐらいの海にも出なくなってしまう。
心に余裕がなくなっているのである。
これでは、生活の豊かさを演出する職業人としては失格なのである。
海に出て本当に頭を上げて遠くを見ていると職業人としての初心に戻れるのである。
そして、処理するのではなく、楽しむことに専念できるようになるのである。
そんなことを経験していたので先の年頭の挨拶が、身に沁みて感じることができた。
だから1996年の目標は「頑張らない!」なのである。
平成8年1月 若潮
あとがき
建築設計って、50をすぎた頃から油が乗り出すらしい。
それまでは、甘ちゃんで青二才らしい。
大御所、丹下健三も50半ばで独立したように記憶している。
矢沢永吉も今年50になるそうだ。
わが青春のキャロルの親分も50になるらしい。
50のロックンローラーに新たな闘志をかいま見た。
自分ラシサを追求することに年令はないらしい。
サクセスを手に入れたくて走り続けた27年ばかり。
実際サクセスを手に入れた今では「自分ラシサ」を求めているという。
そのために日本ではじめての50才ロックンローラーをやり続けるのだという。
私も50になるのが待ち遠しい。
いっぱい経験や知恵を蓄えて、脂ののりきった建築設計をしてみたい。
そのためにはしっかり走り続けていき、認められることが大前提らしい。
しっかり走り続けることは今やっている。
大事なのは、生活者をしっかりやることだろう。
自分と家族と地域と地球に忠実にウソ偽りなくやることが。
平成11年8月15日
小潮
1984年。ある住宅メーカーに就職した。
義務教育を終えて高校、大学へ行くようにあまり深く考えずに就職先を決めた。
そのときはまだまだ前途洋々だったのである。
限りなく広がる社会という世界がいくらでも自分の思うようになると考えていた。
4月1日入社式があった。
住宅メーカーでは日本で1、2を争う企業なので東日本地区だけでも200人くらい新入社員がいたような気がする。
すごく賢くていかにもできそうな奴から、俺にも勝てそうなとろそうな奴までごちゃごちゃたくさん居た。
そんな訳なので、当然のように同じ大学の同級生も何人か混じっていた。しかし、ほとんどのその他大勢は知らない奴ばかりだった。
入社式が終わって、すぐ新入社員研修が始まった。
最初は、新入社員全員でやる研修だった。
営業、総務、技術系みんな一緒の研修なのである。
研修場所にバスで送られて、すぐ全員持ってくるようにいわれていたジャージー・トレパンに着替えさせられた。
研修のお知らせには、スエットやスポーツウエァなどではなくジャージー・トレパンと書かれておりなんだか嫌な感じがするなぁと思っていた。
着替えさせられてすぐに外のグラウンドに集合がかかった。
「時間厳守!じかんげんしゅ!ジカンゲンシュ!」「社会人はジカンゲンシュでなくてはいけません!」学校の先生でもそんなに真剣に子どもに言って聞かせることがないくらいにしつこくまくしたてられた。
今にして思えばその人も給料をもらってやっているのであり、好きでみんなのけつをたたいているのではなかったのだろうなぁと思う。
鳩時計が時報を知らせるように繰り返し繰り返しむなしくしつこく同じことを言っていた。
それでも社会人1日目の我々は、まだ学生時代の怠惰な習慣が抜けていないらしくぐずぐずしながら外のグラウンドに向かっていった。
着いたとたん、「さー!みんなで元気良くー!たいそー!」と元気のいい先輩社員が正面の少し高い台の上で声を上げた。
すると、人気のない四方八方山に囲まれたさわやかな自然の中いっぱいに音楽が流れ始めた。
「大きく広が〜る〜!夢〜!ゆめ〜!ユメ〜!、〜誰でもが願ってる明るい住まい。×○はうす〜!×○ハウス〜!」
すぐにその場から逃げ出したくなってしまった。
こそこそまわりを見渡してみたが逃げ出している奴はいなかった。
逃げ出しているどころかみんなきちんと前を向いてのびたりちぢんだりしていた。
「なんか変だなぁ〜。俺は一生この踊りをおどっていきていくのだろうか。」と心細くなっていた。
その日のうちから具体的な研修が始まった。
名刺の差し出し方や目上の人と応対するときの礼儀などいろいろ教え込まれた。
その中でも特に印象に残った研修は、ロールプレーイングという瞬間劇だった。
家を建てたいというお客さんと家を売りたいというセールスマンになり代わってのにわか漫才みたいなものである。
結構おもしろかった。
得意になってお客の役やセールスマンの役をやった。
「君はなかなか営業のセンスがあるねぇ。」と言われて少しうれしくなりその後の研修も次第におもしろくなっていった。
その研修も1週間ほどで終わった。
その次は、技術系の新入社員だけでやる特別研修が待っていた。
その研修は、そのメーカーの自社工場の一角で行われた。
朝6;30ちょうどにやはり「大きく広が〜る!」でおこされた。
最初の朝は、何事が始まったのかと思った瞬間何とも言えないいや〜な気分になったものだが、不思議とそんなことはだんだん慣れていった。
その研修は建築学科出身の技術系ばかり20人ぐらいのメンバーだった。
大学の成績は中の中位で卒業していたので一応仕切り直しで社会人になったらがんばろうと思っていた私は、結構真剣に研修に取り組んだ。
その研修は2週間ぐらい続いて充実した中で終わりを迎えた。
終わって、その翌週勤務先に戻ると80人ぐらいいる営業所の親分である所長に呼ばれた。
「君はこの営業所が始まって以来の人物だ。」と言われ、「はぁ...」と答えると「技術系の研修では、トップで終了したそうじゃないか。営業所の誇りだよ。その気持ちを忘れずに頑張ってくれたまえ!」とのことだった。
人はほめて育てろと言うことがあるらしいが、まさに私は、その一言でしばらくは、頑張ることができた。
しかし、一生懸命頑張れば頑張るほどになにかが違うのではないかというぼんやりとした疑問が沸いてきていた。
俗に言う新入社員の五月病というやつだったのかもしれない。
自分には、まだまだ限りない可能性があるのではないか。
このまま一企業の歯車としてやっていって悔いはないのだろうか。
一生懸命やっていたからなおさらこの一生懸命さは誰のためなのかという疑問がこみ上げてくるのだった。
自分のためなのか、会社のためなのか。
お客さんのためなのか。
大学4年の時に垣間みてしまった建築の世界は、まさに自分と対峙しながらものを作り上げていく精神的な世界だった。
戻りたいと思った。
自分を表現する手段としての建築行為に未練を感じていた。
しかし、そのときの戻りたいと思う気持ちは、社会という大きなうねりの中で自分の船をこぎ続けることが何となく嫌で、まだまだ学生のままでいたいという甘ったるい気持ちだったように思う。
では!と建築の道をめざすということでもなく悶々とした日々を過ごしていた。
勤務先での毎日は、多くの先輩からいろいろなことを教わることが多く表面的には充実していた。
「会社なんて社員のことなんかよりも会社の業績が上がることの方が大事なんだからそんなに一生懸命やっても無駄だよ。」
「おまえ、適当に息を抜かないと、会社につぶされてしまうぞ。」
「上司にはハイハイって言っておけばいいんだよ。」
というネガティブな教育的助言。
「絶対、誰かがどこかで見ているから適当にやっちゃダメだぞ」
「俺は、先輩だからおまえにおごってやるけど、おまえも後輩にはその分きちんと面倒見てやらないとダメだぞ。」
「今、誰のために仕事をしているかしっかり見極めることが大事だぞ。」
といった人生教訓的な助言。
それらは、それぞれ血となり肉となっていった。
しかし、誰のために仕事をしているのか見極めろと言っていた先輩は、上司のごきげんを取ることがとってもうまく、上司の方を向いて仕事をしていた。
全体的には、会社員とはそんなものなのかと失望してしまうくらい夢のないことが多すぎた。
住宅建築に携わっている企業に属していた私だったが、会社員とは何ぞやということ以外に会社から得られる建築的な刺激はほとんどなかった。
五月病が治りきらないまましばらく悶々としていた。
酒を飲んでは、このままでいいのかという思いに悩まされた。
自分としては、何のために仕事をするのかということも疑問だった。
自分のためなのか、家族のためなのか、会社のためなのか、お客様のためなのか。
良くわからなかった。
ただし、良くわからないなりにも会社や上司のためにだけは仕事をする気にはなれなかった。
何となく自分のためと言うよりは、お客さんのために仕事をしていると思った方がやる気が出た。
会社のために仕事をしているのではないと思うようにした。
私は、9;00始業なのだから9;00に間に合うように出社し始めた。
というのは、その営業所では、慣例的に8;00には全員出社していて8;30にはてきぱきと仕事を始めていた。
早起きは、三文の得とあるようにそれはそれでよいと思うのだが、それは自ら率先してやることであり会社の慣例だからそうするというのは納得いかなくて就業規則通りわざと9;00ぎりぎりに行くようにした。
案の定、先輩社員からの風当たりは次第に強くなった。
「おまえなぁ、俺より遅く来るなんて10年早いよ。」とか「明日の朝、8;00までにこの書類をコピーしておくように。」とかあからさまに私の行動に嫌がらせをしてきた。
しかし、私としては勤務中は一生懸命仕事をしているという自負があったので気にせず頑固に毎日一番遅く出勤していた。
そんな私だったのでいつしか誰も文句を言わないようになっていった。
ある日、2年先輩ではあるが同じ歳の人から「いいよなぁ。佐山は。いつも遅く来ても誰にも文句を言われないんだから。」と言われ、ニヤッとしていた。
その年の夏休みに一週間ぐらい休んだあと、出勤するのがいやになってしまった。
続けても企業の中で泳ぎわたる処世術しか身につけられないと思ったのである。
おおいに悩んで出した結論は、このまま社会人として生きていくのであれば長期の職業人としての戦略を立てようということだった。
今やっていることは、無駄にはしたくない。
しかし、このまま終わりたくない。
であればここで吸収できるものは徹底的に吸収して次のステップアップの材料にしよう。
石の上にも3年。
この会社には3年は居よう。
そしてそれを財産に転職しようと思ったのである。
サラリーマンとは何ぞやという財産は貴重な財産になると自身に言い聞かせた。
20代は3回転職して3種類の経験を徹底的に吸収する。
30代は落ちついて建築の世界に身を置く。
でもまだ若輩なので30代は積極的に吸収しつつ、吐き出す日々にする。
40代はじっくりと建築と向き合いながら職能を発揮する。
そしてそこまで一生懸命走り続けて50を迎えたら山の中に入り込み、自分の求めるものに集中したいと職業人生を組み立てた。
20代は修行、30代は修行と貢献、40代は貢献、50代は何もしない。
そう考えるようになって、そのときやっていることの意味を自分なりに納得させることができて、悶々とした日々から抜け出していった。
30代中盤の今現在は、予定通りにはいかずに修行と貢献というよりは修行修行に終始している毎日である。
人生とはなかなか思う通りにいかないものであるが、何とか50代には自然の中で悠々自適に建築とマダイに取り組んでいたいものである。
平成7年11月 小潮
1983年。大学4年生。春から夏にかけて就職活動をしていた。
大学生活の前半と中盤はアルバイト、サーフィン、麻雀で終わってしまった。
4月に無事大学4年生になった。
そのころ私の通っていた東京理科大学は、留年せずに卒業することはとても難しいと聞かされていた。
特に私のような学校にも行かず、建築の専門課程にも興味を示さず、ただれた日々を送っていた者には、当然留年のお達しが来るはずだった。
しかし、マス大学の欠点である適当にやっている奴に目が行き届かないという盲点を見事にくぐり抜けてしまい4年生になってしまった。
私は、ところてん的に4年生になってしまったのである。
本音は、強制的に「もー1年やりなさい!」ときっぱりと言ってほしかった。
私の居た東京理科大学は4年生になると研究室に所属することになっていた。
そこで、今までの大学生活の総決算とでもいうべきそれぞれに特別な研究課題に取り組むのだ。
研究先は、各自好きなところを選ぶことになっていた。
やはり、研究室といっても教授という人が経営している学習塾みたいなものであり、人気がある研究室には希望が殺到する。
私が、目を付けたのは、それまで何となく若くてものわかりが良さそうだなぁと思っていたかっこいい講師の研究室だった。
今思うとその先生はなんと今の私と同じ34歳であったのである。
私のように不純な動機のかっこよさで選んでいる学生がたくさんいて、そこは一番人気だった。
たくさんの学生の中から活きの良さそうなヤツを選ぶために面接があった。
「あなたの好きな建築家は誰ですか?」いきなり来た。
「好きな建築家は、誰も居ません。」「・・・・・;」
「私は自分が大好きなので、自分が暮らしたいと思う空間を創りたいと思います!」
「そーか、次っ!」
どういう訳かその研究室にも入ることができてしまった。
結構うれしかった。
研究室に所属するようになって、はじめて自分の居る場所ができたような感じで、大学へは以前より行くようになった。
それまで私は自分で建築学科に所属はしているけれどもその道のことはなにも知らず道をはずれかかっていた。
研究室の中のみんなは、しょっちゅう磯崎新がどうの、安藤忠雄がどうのとわかったような感じで議論していた。
私は、軽いカルチャーショックを感じながらその世界に少しずつ引き込まれていった。
しかし、そのころの関心事はまだまだ海と麻雀だった。
サーフ・ボードにまたがり遠くの波を見つめ大きな波を待っていたり、相手の顔色を横目で見ながら指の腹に感じる雀牌のデザインに命を懸けたりしている方が楽しかった。
5月にもなるとまわりが、面接面接と騒ぎ始め出した。
みんな校舎のまわりの公衆電話で電話をかけているのである。
メモ用紙を見ながら必死に電話をかけていた。
6月にもなるとやはりところてんの4年生としても来年のことが気になってきた。
そろそろやるかという気になってきたところで、自分の歩きたい道がわからない。
「心理学的空間占有に関する研究」というのが自分の研究テーマになっているけれど、9月の提出までに時間があるので全く手を付けていない。
自分の歩きたい道がわからない。
まわりは、磯崎新。安藤忠雄。面接面接。アポアポ。急いでいた。
そんな中、大学から帰り自分の部屋で酒を飲んでいた。
酔ってくるとまわりのものにはまりこんでしまう癖があった。
レコードを聴き、英語の歌詞カードを見ながら十分意味もわからないくせに泣けてきたり、テレビドラマにはまって脚本家の思うとおりに大泣きしてしまったり、知らない人が見たらこの人おかしいんじゃないかと思うくらい入り込んでしまう癖があった。
そのときもはまりながらTVドラマを見ていた。
「あ〜あ!」と頬を手で拭ったとたん、ふと始まったコマーシャルがその手を止めた。
のりのいいリズムにパンティが踊っていたのである。
最初はきれいな足しか見えないコマーシャルなのだが最後に画面いっぱいにパンティがたくさん出てくるのである。
「クール・ストラッティン」という足首しか見えないジャズのレコード・ジャケットが大好きだった私としては何者かにとりつかれてしまったように唖然としてしまった。
(スクエアのファースト・アルバム;海辺で後ろ姿の女性のパンティが見えるやつ、もいいねぇ)
なにかいきなり後頭部を殴られてしまったような感じだった。
自分もこんな仕事がしたい!人の心の隙間にぐいっ!と入ってしまって「どうだ!」ってなことができるような仕事。
単純なのである。CMの仕事がしたいと思ってしまった。
それから真剣に就職活動を始めだした。D通、H報堂、その他いろいろ...片っ端から広告代理店とアポを取った。
そうはいうものの、建築関係のところもとりあえずしっかりとアポを取っておいた。
7月にもなるとアポそして面接、アポそして面接の日々が続いた。
8月。
思うようにいかない中で一つ内定がとれた。
それは、とりあえずのアポイントメントとして取っていたある住宅メーカーだった。
まあ、一つ内定がとれたんだからこれからは好きなところを攻め続けられるな。
と、楽観的になり海と雀牌にあつくなっていた。
そのあとの広告代理店攻撃は、D・H続けて3次試験で敢えなく終わり「まー、いいやー」でケリが付いてしまった。
9月。そんなわけで、とっても簡単に就職先が決まってしまった。
しかし、そのおかげでまた研究室のカルチャーショックの日々と海と雀牌の生活がまた始まった。
人生とは不思議である。
大学生活も4/5終わったところで少しずつ受け続けてきた建築カルチャーショックがぶくぶくと発酵して大きな勢いになる気配が感じられた。
就職して、泣いた。悔しくて泣いた。
本当に泣いたのである。
サラリーマンが嫌で泣いたのではない。
毎日毎日、滅私奉公の毎日が嫌だったんじゃない。
大学生活最後のところで覗いてしまった建築デザインのおもしろさ、奥深さ。
自分を表現する手段である建築デザインの世界への傾倒。
社会に出てから、理想と現実の狭間で頭の中がぐちゃぐちゃになってしまった。
組織と個人というテーマでも悩んだ。
個人でできる可能性は限られている、組織でできる個人の可能性も限られている。
どっちを選ぶのか。
歯車だけにはなりたくなかったが、毎日『おまえは、ハ・グ・ル・マ!』と飼い慣らされていくような感じがなんともいえなくいやだった。
酒を飲んだ。
酒に飲まれた。
会社の同僚は、5月病で出ていく。
いいな、とも思った。
しかし、私には行く道がなかった。
行きたい道は漠然とあったのだが、それはところてんの時とは違う勇気のいる道だった。
考えた末にある決断をした。
つづく 平成7年10月 小潮
あとがき
前回から話が飛躍しているが、その間の2〜3回分は今読むとあまりにも稚拙なので掲載は止めた。
今回は社会に出ることを安易に決めてしまったことの話を掲載した。
社会に出て初めて、自分はどのようにして生きて行くんだろうと実感した。
いや、自分はどういう生き方をしたいのだろうということだったのかもしれない。
まわりをキョロキョロしないで、二本の自分の足で歩いていきたいとも思った。
そのためには、どうしたらいいのかと当時真剣に考えたものである。
いま生き方そのものに迷いや不安はない。(欠点はいっぱいあるものの)
ただ、今のやり方でいつまで生きていけるだろうかという不安はある。
『やっぱり、事務所で鉛筆握って、死んじゃうんだろうな』とある先輩は力弱く笑っていた。
私は、山の中で薪ストーブに心地よくなりながら、夢の中かで静かに人生をおわりたい。
なんて、まだまだ先のことではあるが。
どんどん生きていくのだ。
1999年6月9日
目の奥に広がるイメージと遊ぶのが好きだった。
1976年夏、高校一年生の学校帰りだった。
本屋で立ち読みしたポパイ創刊号が目の奥に焼き付いていた。
当時のポパイは今のやわなポパイと全く違っていた。
硬派なアメリカ若者文化の情報伝達紙だった。
スケボー、ピックアップトラック、アウトドアライフ。
いまでこそ、なんでもない日本中に蔓延している文化だが、当時はまだ1ドル360円の時代でとても珍しかった。
アメリカからの情報自体にも360円/$くらいの価値があったような気がする。
とにかく、頭の中を西海岸の青い空と青い海でいっぱいにしながら自転車をこいでいた。
家についても興奮していた。
鞄を放り投げ、ベッドに倒れ込むとまた目の前に青い空と青い海が広がった。
なぜかその自由な明るさが目の奥に焼き付いていた。
もっともっと知りたくなった。
一度興味を持つととことん追求してみたくなる癖がまたうずいていた。
ポパイ、メンズ・クラブ、ウッディライフ。
アメリカ風俗の情報を毎月毎月楽しみにしていた。
そんなアメリカ風俗で頭いっぱいにしながら毎日退屈な高校の授業をぼんやりと聞いていた。
それは、いつもとかわりばえのしないある日の5時間目の時だった。
突然、産休することになった現代国語の先生の替わりに別の先生がやってきた。
年は50才ぐらいに見えたが、とてもあか抜けていて、物わかりのよさそうな女の先生だった。
来ていきなり教科書をしまってくださいと言った。
なぜかわくわくした。
それまでのきゃんきゃんうるさい女教師に比べて、ほのかな色気を漂わせた知性あふれる熟女先生だったからなのか、教科書はいらないといったからなのかよく覚えていないが、思春期の私はとにかくワクワクしていた。
おもむろに熟女先生はスーツの右ポケットから単行本を取り出した。
富島健夫、佐藤愛子か、はたまた宇野鴻一郎か(そんなアホな)。
熟女先生はふっとひとつ小さなため息をついた。
そして「みなさん。これからある短編小説を読みます。」
ドキドキした。
「これから私が読む情景描写を銘々自分の頭の中でイメージしてください。好き勝手に想像して結構です。」
頭の中はもう十分膨らんでいた。
『空がぼんやりと紫色にあけてきた。男たちはそれぞれ焚き火を見つめながらコーヒーを飲んでいた。』
『女たちはベーコンと豆を炒め』
『その何気ないいつもの朝食が始まり、やがて空は紫色からブルーへと色を変えていった』
「これが、私の一番好きなジョン・スタインベックの書いた『朝食』という短編小説です。」と熟女先生。
膨らみきった頭の中の期待ははずれたものの、しっかりと頭の中は紫色からブルーに染まっていた。
なぜかとってもかっこよかった。
読み方が良かったのか、熟女先生が良かったのか、覚えていないが、朝焼けの中でカウボーイが焚き火を見つめながらコーヒーをすするシーンが目の奥に焼き付いた。
20年近くたち、私の思い入れも入ってしまい、実際の小説は内容的に違うかもしれない。
しかし、そのときはかっこよかったのである。
目の奥に広がるイメージをいつまでも大切にしておきたかった。
その熟女カウボーイ事件のあたりから、ポパイやメンズクラブなどではヘビービューティー・アイビーなるアメリカン・ファッションをさかんに取り上げ始めていた。
そのヘビアイは、それまでの都会的なアイビーとは違っていた。
自然の中で活きていくための必然的なファッションであると各紙は伝えていた。
赤黒のチェックのシャツは狩りに出かけて獲物と間違われないための必需品。
ダウンベストの後ろの少し垂れ下がっているのはキドニーウォーマーといって肝臓を冷やさないための必需デザイン。
バンダナは時として救急用の三角巾、とある時はコーヒーを入れるフィルターと万能七変化する必須アイテム。などなど。
焚き火の前での朝焼けのコーヒー・カウボーイがとても気に入っていた私はふーんと冷静さを装いながらもズズズッと一気に引き込まれていた。
そのころに創刊されていたウッディライフにログハウスなるへんてこりんな家が紹介されていた。
相変わらず、アメリカ情報を漁っていたとき目に飛び込んできた。
カナダの山奥で一人で木を切り倒して自分で作ってしまった家だそうだ。
アメリカでは自分の家ぐらいは一人でつくってしまうくらいでないと一人前の男ではない、らしい。
開拓時代から続いている一般常識ということだった。
また、かっこういいと思ってしまった。
今でこそログハウスなんて珍しくはないが今から20年前の話である。新鮮だった。
こんなことを将来の仕事にしていけたらいいなあと思いながら、また目の奥のイメージを楽しんでいた。
木こりになりたい。
自然の中で暮らしたい。
北海道生まれで、ものごころつくころまでほんとに山の中に住んでいたわたしだったが、真剣にそう考えていた。
そのときから大学は建築学科かなあとも考えるようになっていった。
つづく
追伸:
今現在、私が手掛けているプロジェクトの一つにログハウスの設計がある。
施主は、一度ログハウスを建てたことのある方で、メーカー主導の設計に満足できなかったということで「また建てたい!」と私のところへ話が舞い込んできた。
円高でもあり、アメリカから直接材料を輸入して本物を建てたいというこだわりのある方でもある。
その方の夢の実現のためにも私がひと肌もふた肌も脱ぐことになった。
実の所私の夢の実現でもあるのだ。
それではいざ行かん!と今年の9月に現地(シアトル)に出向き資材をチェックしてくる予定である。
予算的には、現在主要ログ・メーカーで建設されている工事費の70%程度で夢が実現できそうでまたわくわくしている。
思い続けているといつかはかなうらしい。
また、目の奥のイメージが限りなく広がっている。
夢は喰えば喰うほど大きくなっていく。
平成7年7月 中潮
あとがき
今の私の根元を流れる基本思想が、確定した実話である。
ポパイ、『朝食』、ヘビアイ、ログハウス。16歳の目に焼き付いて離れなかった。
今の私の設計思想の奥深いところをとうとうと流れている基本理念なのである。
たぶん死ぬまでひきずることになるだろう。
私は、それを望んでいる。
1999年4月28日
私の建築家志望は、隣のオジサンと父との会話から始まった。
「希人君は、将来何にさせるのかね?」
「これからの世の中は、何がいいんだろうねぇ。」
「これからは、腕に職をつけておいた方がいいかもしれないなぁ。建築家とか、医者とか、パイロットとか。」
「そうかもしれないねぇ。」
「今のうちから考えさせておいた方がいいよ。」
「でもまだ子供だからねぇ。」
確か私が中学校一年生になったばかりの頃だったように思う。
その頃は、まだまだ将来のことなど考えたこともなく、そんな大人の会話を黙って聞いていた。
当時は、そんなことより中間テストや期末テストがやってくるまでの間、いかに遊び続けるか!ということの方が、日々の重要検討事項だったようだ。
しかし、隣のオジサンが言っていた「今のうちから考えさせておいた方がいいよ。」という言葉が頭の片隅に残ってしばらく離れなかった。
『なにになるのかねぇ。僕は...』しばらく考えてみたが今ひとつ実感がわかなかった。
その頃、ラジコンに心を奪われていたので好きなラジコンをいつでもいじれるラジコン屋がいいかもしれないと密かに思ってみたりした。
『僕は、大きくなったらバスの運転手!』と同じレベルである。
また、当時、中学に入って最初の音楽の時間にビバルディの四季を聞かされた。
その新鮮なリズム感とメロディに一発で引き込まれてしまった。
これがきっかけとなり、バロック音楽から古典派までにのめり込んでいった。
その頃、北海道FMでは、朝6:15から”バロック音楽の楽しみ(皆川達夫)”という渋い番組を放送していた。
ビバルディにはまって以来、その番組を布団の中で聞くのが日課となった。
今でも、NHKFMの朝一番のテスト放送用のジングルが当時と同じなので、それを聞くと甘酸っぱいような感触がよみがえってくるのだ。
毎朝布団の中で、指揮者になりたいと夢の中でタクトを振っていた。
そんな日々を送っているある日、私の友人の松山君が体育の授業中に複雑骨折してしまい、緊急入院してしまった。
入院は長期間になることが予想されたため、何か退屈しのぎになるようなものをお見舞いの品として贈ることがその日のホームルームで決まった。
なにを贈るかみんなで検討した。
日頃、大人びていて先端の風俗情報なども知っている松下というやつがいた。
彼には、4つ上のお兄さんがいて、いつもお兄さんから仕入れた話を自慢げに話していた。
「ビートルズの赤と青がいいよ。」彼は言った。
『また、兄さん情報か。ちぇっ!』と少しだけうらやましく思った。
しかし、その『びーとるずのあかとあお』っていったいなんだろう?なにやら長髪の外人ロックグループのようだということまでは気がついたのだが、『あかとあお』って?なにかなぁ。
見舞いの贈り物は、なんだかよさそうだ、松下が言っているんだから今はやっているんだろう、というムニャムニャした雰囲気の中、その『あかとあお』に決まった。
そしてどういうわけか、私がそれを買って松山君のお見舞いに行くことになった。
「今日入院したばかりなので、一週間後くらいにお見舞いするように!」といわれながら、みんなから集めたお金を手渡された。
その日のうちに、レコード屋に行った。
『病院だから、レコードよりはカセットの方がいいな。』と勝手に思っているうちにレコード屋についた。
そのとき、その『あかとあお』は、キャンペーン中のようですぐに見つけることができた。お金を払いながら、すこし大人になったような感じがした。
家に帰っても、その包みが気になり、早く一週間がたたないものかとウズウズしていた。
待ちに待った一週間が過ぎた。
放課後、一目散に病院に行った。
「これ、みんなからのお見舞い!聞いて見ようよ!」
松山君の病状を聞くこともせず、中身を見る前から、聞こう聞こうと催促してしまっていた。
「ら〜ぶ、らぶ、みっどぅ、ゆ〜、の〜、あいらぶゅ〜」
初めて聴く曲に聞き惚れてしまった。なんか大人って感じなのである。
松山君は、お兄さんがいるわけではなかったが、ビートルズには詳しかった。
いろいろ教えてくれた。
私はいつまでたっても帰ろうとせず、繰り返し繰り返しカセットを聴いていた。
根負けしたのか、松山君は、そのカセットを私に貸そうと言ってくれた。
「いや〜、そんなのわるいよ〜。」といいながら、すぐに鞄にしまい、「わるいね!わるいね!」といいながら病室をあとにした。
それ以来、ビートルズのとりこになり、バンドを組むようになっていった。
ギターとバンドに明け暮れる中学校生活を送っていた。
三年生にもなると先生は、「将来のことをそろそろ真剣に考えなければなりません。」と日々言うようになった。
『なんになるのかねぇ。僕は...』前にもそんなことを考えたことがあったような気がしていた。
『音楽で飯が食えるといいなぁ。でもピアノが弾けないんじゃ、無理か...でもゲイ大に入れればもしかして...』
『パイロットなんかもいいなぁ。建築家っていうのもいいとどっかのオジサンが言ってたよなぁ...』
『医者もいいといってたけど。血を見るのがいやだからヤメトコ...』
ある日、父にボヤ〜ッとながら将来のことを話してみた。
すると「パイロットになるためにはボーエイ大学、医者になるためにはボーエイイカ大学、建築家になるためにはホッカイドー大学!」ときっぱりと言ってきた。
いつかどこかで聞いた話だ。
私は、よくわからないまま、部屋に戻った。
ギターを片手に「ボーエイ大学、ボーエイイカ大学、ホッカイドー大学、そして、ゲイ大」とぶつぶつ、つぶやいていた。
パイロットは、目が悪いのでだめそうだ。
医者は、血がいやなのでなりたくない。音楽では、飯が食えそうにない。
そうなると前に隣のオジサンが言っていたように建築家しかないのか。
数学と理科が好きで、音楽も好き。となると建築家ってのもいいのかもしれない。
何故か、隣のオジサンの残した言葉から選択範囲を広げることもせず、進路は決まったようなつもりになっていた。
「高校に行くにあたっては、自分の将来を真剣に考えなければなりません。」といわれながら、あまり深くも考えずに、普通高校に入学していた。
相変わらず、バンドは続けていたものの何か物足りなさを感じていた。
学校帰りにふらっと本屋に立ち寄った。
そこには、『POPYE!創刊!700円!』とあった。惹かれるように手に取った。
まぶしいくらいの太陽とそこで繰り広げられているアメリカ西海岸の自由なライフスタイルが目に焼き付いた。
「ほしい!」ポケットをまさぐる。
その月の小遣いは残り230円となっていた。
食い入るように見ていると、一緒にいた増田が2才年上のお兄さんから聞いていたらしく、その辺のアメリカ事情を教えてくれた。
「サーフィンのこと、ピック・アップ・トラックのこと、スケボーのこと、UCLAのこと、リーバイスのこと、エディー・バウアーのこと、アウトドアライフのこと。」聞くだけでクラクラしそうだった。
私は、何かいや〜な予感を感じながら、家に向かって思いっきり自転車をこいでいた。
つづく
平成1995年6月 中潮
あとがき
今の私の根元を流れる基本思想が、発生し育ちつつある時期のことである。
今では、当時のようにのんきに行き当たりばったりの受験というわけにはいかないだろうが、私の時分は、おおらかだった。
北海道の田舎ものだったからかもしれない。
ただ、感謝しているのは、行き当たりばったりの生活を送る息子に対して、こうしなければならないというような親の決めたレールがなかったことである。
隣のオジサンの決めたレールに乗って走りだしてしまったのかもしれないが...。
1999年3月25日
どれだけ道を歩いたら
一人前の男として認められるのか
いくつの海をとびこしたら
白い鳩は
砂でやすらぐことができるのか?
何回、弾丸の雨が降ったなら
武器は永遠に禁止されるのか?
そのこたえは友達よ、風に舞っている
こたえは、風に舞っている
1962年4月 ボブディラン
この曲を聴くといつでも勇気づけられる。
学生時代は、特別な問題意識もなく、ただぼんやりと毎日を過ごしていた。
ところてん式に大学を卒業し、社会人生活の五月病も少し、おさまった頃、「いつになったら、一人前の大人(いや、男)として認められるようになるんだろう?」と思っていた。
絶対的な自信というものが持てず、いつも、あーではないか、こーではないかと迷っていた。
そして、いつになったら、ゆっくりと自分自身を見つめながら、身の丈にあった自分らしい生き方が、できるようになるのだろうかと考えていた。
しかし、どのくらい走り続けなければならないのか?考えると気が遠くなりそうになった。
そんなときでも、この曲を聴くと「おまえだけではなく、みんなそうなんだ。」と勇気づけてくれるのだった。
連載の話を頂いたときは「はい、はい、いいですよ!いいですよ!」と喜んで引き受けた。
なにしろ自分の書いたエッセーが活字になるのだ。
頭には次々にひいきにしている人気エッセーが浮かび顔もほころんでくる。
が、しかし、顔であるタイトルはなににしようか、と考え出してあわててしまった。
基本の、「起業家をめざす若い人々に向けて、佐山は何を語るべきか」という大問題にぶちあたってしまったのである。
根っからの理系人間である私は、実のところ作文、小論文、書くこと全て大の苦手なのだった。
会社をおこすにあたって、どんなことでも引き受けよう、小さなことでも、人が嫌がることでも、何でも喜んでやろう、と密かにきめていた手前、前述のようにしっかりと喜んで引き受けてしまっていたのである。
しかしながら、これから日本や世界を相手に事業をおこそうという、優秀且つ血気盛んな若者に何を語るというのか・・・。編集部からは、「タイトルは、勝手に決めて下さって結構ですよ。」といわれていた。
そのときは、「そうか、そうか、好きに決めていいんだ。」としか思わなかったけれど、いっそのこと、編集部から「私の起業失敗談」とか「若者よ、起業はやめろ!」とかいうタイトルで書いてくださいとはっきりと言われる方が良かったような気がしていた。
そんな中、まだ仕事の依頼も少なく、時間だけはあったのんき起業家としては頭を悩ませながらも「気分を変れば妙案も浮かぶだろう。」と平日のマダイ乗合船に乗り込んだ。
エッセイの締め切りわずかというのに大胆不敵な行動に出てしまったのである。
若者に語るべき戦略も哲学も持ち合わせていないのだからしょうがないのである。
その日は平日にもかかわらず、マダイ戦士が15名も舟に乗っており、満席状態であった。
けっこう暇な人が多いもんだ・・・と感心し、平日の昼間に釣りを楽しむというのは自由業ならではの贅沢なのかもしれないと後ろめたさを感じつつ、船に揺られていた。
その日は吹かれているのが心地よい、さわやかな風が、釣りバカ達を包んでいた。
「気持ちいいなぁ。やっぱり釣りは結果ではなくプロセスを楽しむスポーツだ...。」と、魚信が無いことの言い訳にしながら、風に身を任せていた。
そんなときこの連載のことが、ふと頭をよぎった。
「あーあ、帰ってからあの宿題が待ってるんだよなぁ。いやだな〜。でも、作文嫌いの俺にいい文章がかけるわけもないしな〜。」
「何かを伝えよう、なんて立派なことを考えるからだめなんだよな。
とりあえず、この心地よい風のように、風の吹くまま気の向くまま、思いついたことを書いてみるかなあ〜。」「ん....!そうだ。タイトルは、ボブディランの”風に吹かれて”がいいな。歌も好きだし、なんか意味もありそうだしな、よし!よし!」
そのとき、竿にマダイ特有の「カン!カン!カン!」という当たりが伝わってきた。
「おお、マダイちゃん!」とは思いつつも、何が釣れているやらわからないのが釣りの醍醐味。
しかし、しっかりと重いマダイの三段引きが腕に伝わってきた。そして、ゆらりと海面にその美しいピンク色の姿をあらわした。
慎重に舟にあげると、30cm強の小振りではあるが美しいマダイである。
チャームポイントのブルーの斑点がたまらない。
「少し小さいけど、今日は、おまえでよし!としておこう...」
その日の釣果がこのマダイだけであったことは言うまでもない。
いつめぐってくるかわからない大物を求めて、日々努力を続けていくことがチャンスをものにすることにつながるのだ!あきらめずに追い求めるものにだけ栄光は与えられるものなのである!
と、釣りのことなのか、ビジネスのことなのかわからないポリシーではあるが、佐山は、そう信じている。
そんなわけで、佐山が背伸びせず、思いつくまま、可能な範囲で起業家に独り言をぶつけていこうと勝手に決めてしまった。
そんなわけで、タイトルは、「風に吹かれて」なのである。
今後とも宜しくおつきあいのほどを。
1995年5月 小潮
あとがき
1995年の春、縁があって川崎にある日本起業家協会が発行する「起業家」という冊子への連載を引き受けることとなった。
当時(株)生活空間研究所を開業してから1年あまり。
まだまだ不況の荒波もいまほど厳しくなかった頃である。
今でこそ、当時のように平日昼間っから釣りをする贅沢は、できなくなってしまったが、生活自体を楽しむ余裕は、いつでも持っていたいと思っている。
1999年3月7日

▼ 記事へのコメント
-
2013.07.13 : by すず : こんにちは。久しぶり
-
2013.03.26 : by m.sayama : 実のところ、ビートル
-
2013.03.20 : by bantou : こんにちは。私もJa
-
2013.01.04 : by m.sayama : bantouさん、お
-
2012.12.31 : by bantou : こんにちは。薪ストー
-
2012.09.17 : by m.sayama : コメントありがとうご
-
2012.09.16 : by 葉山とうきち : 最近津波情報が大きく
-
2012.08.22 : by m.sayama : 塚越様
コメントに気
-
2012.07.14 : by m.sayama : くらさま。コメントあ
-
2012.07.12 : by くら : 本当に恐ろしかったと
過去のコメント一覧を見る